○川上村身体障害者・児補装具給付事業実施要綱
平成13年3月30日要綱第5号
改正
平成19年3月26日要綱第8号
平成28年3月17日告示第42号
川上村身体障害者・児補装具給付事業実施要綱
第1 目的及び基本的事項
1 補装具は、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、
また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・
助長すること等を目的として給付することにより、その福祉の増進に資することを目
的とする。
このため、補装具の給付に当たっては、身体障害者及び身体障害児(以下「身体障
害者・児」という。)の身体の状況、性別、年齢、職業、通学、生活環境等の諸条件
を考慮して行うこと。
なお、その際、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮するこ
と。
2 補装具を必要とする身体障害者・児及び現に装用している身体障害者・児の状況を
常に的確に把握し、これにより計画的な更生援護の措置を講じるとともに、装用状況
の観察、装着訓練の指導等を積極的に行うこと。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)及び児童福
祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)以外の関係各法の規定に基
づき補装具の給付等が受けられる者については、当該関係各法に基づく給付を優先し
て受けるよう取り扱うものであること。
4 補装具の給付を円滑に行うためには、製作等を委託する業者の設備、技術が整備さ
れることが必要であるので、公立補装具製作施設についてその設備、技術者等の整備
強化を図るとともに、民間の補装具製作施設等に対してもその旨周知を図ること。
5 補装具製作者との委託契約に当たっては、その設備、技術等を検討したうえで適切
な業者を選定して行うこととし、契約の締結に際しては、別紙契約書(案)を参考と
すること。
6 この実施要綱における川上村の事務は、その所管区域につき、社会福祉法(昭和26
年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長に委任することができる。
第2 補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の運用
1 価格は、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171
号及び同第187号。以下「告示」という。)に定める主材料、工作法又は基本構造、
附属品等によった場合の最高額として定められているものであり、各種目における型
式等の機能の相違及び特性等を勘案のうえ、画一的な価格の決定を行うことのないよ
う留意すること。
2 身体障害者・児の障害の状況その他真にやむを得ない事情により、告示に示された
補装具の種目、型式、価格等によることができない補装具(ストマ用装具を除く。)
(以下「基準外補装具」という。)を交付する必要が生じた場合の取扱は次のとおり
とすること。
(1) 基準外補装具の交付の必要性及び受託報酬の額等については、更生相談所又は
指定育成医療機関(児福法第20条第4項に定める指定育成医療機関をいう。以下同
じ。)若しくは保健所(児福法第18条の3第3項の規定に基づく療育の指導等を実
施する保健所をいう。以下同じ。)(以下「更生相談所等」という。)の判定に基
づき村長が決定するものとする。
(2) 指定育成医療機関又は保健所は上記の判定を行うに当たっては、必要に応じ、
補装具の構造機能等に関する技術的助言を更生相談所に求めるものとする。
3 受託報酬の額が告示本文第1項に掲げる額の100分の95に相当する額とするものは、
国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は民法(明治29年法律第89号)第
34条の規定により設立された法人の設置する補装具製作施設が自ら製作した補装具に
ついてのみ適用されるものであって、当該施設が民間業者の製作した補装具をあっせ
ん又は取次販売する場合には適用されないものとする。
4 補装具の交付数は、原則として1種目につき1個であるが、身体障害者・児の障害
の状況又は職業更生上等特に更生相談所等が認めた場合は、2個を交付することがで
きる。
5 耐用年数は、通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数
が示されたものであり、交付を受けた者の作業の種類又は障害の状況等によっては、
その耐用年数に相当の長短が予想されるので、再交付の際には実状に沿うよう十分配
慮すること。ただし、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失き損した場合は、
耐用年数のいかんにかかわらず、新たに必要とする補装具を交付することができるこ
と。
6 修理基準の種目欄、型式名称欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理
が必要な場合には、他の類似種目等の修理部位を参考とし、又はそれらの個々につい
て原価計算による見積等により適正な時価を決定し、修理できるものとする。
第3 給付の申請及び判定
1 村長は、身体障害者から身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に
より、「補装具交付・修理申請書」(様式第1号)の提出を受けた場合において、そ
の申請が義肢、装具、座位保持装置、眼鏡(色めがね、矯正眼鏡、コンタクトレンズ
を除く。)、補聴器、車いす(手押し型車いす(レデイメイド)を除く。)、電動車
いす、歩行器及び頭部保護帽(オーダーメイド)の新規交付に係るものであるときに
は、補装具の給付の要否について「判定依頼書」(様式第9号)により、更生相談所
の判定を求めなければならない。
これらの種目については、再交付又は修理に際しても、特に医学的判定を要しない
と認められる場合を除き、同様とすること。
なお、盲人安全つえ、色めがね、点字器、人工喉頭(電動式に限る。)、収尿器、
ストマ用装具及び歩行補助つえ(つえに限る。)の交付及び修理に際しては、更生相
談所の判定を要しないものであり、また、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、人工
喉頭(笛式に限る。)、手押し型車いす(レデイメイド)、頭部保護帽(レデイメイ
ド)及び歩行補助つえ(つえを除く。)の交付及び修理に際しては、補装具交付・修
理申請書等で判定できる場合は、更生相談所の判定を要しないものであること。
2 村長は、身体障害児から「補装具給付申請書」(様式第2号)の提出を受ける場合
には、医師(原則として指定育成医療機関又は保健所の医師をいう。)の作成した「
補装具給付意見書」(様式第11号)を添付させること。ただし、その申請する補装具
が盲人安全つえ、色めがね、点字器、人工喉頭(電動式に限る。)、収尿器、ストマ
用装具及び歩行補助つえ(つえに限る。)の交付(再交付又は修理を含む。)に係る
ものである場合は、補装具給付意見書の添付を要しないこと。
3 基準外補装具を交付する場合は、1項の更生相談所の判定を要しない種目に関する
規定並びに前項の補装具給付意見書に関する規定にかかわらず第2の2項により取扱
うものであること。
4 義肢、装具及び座位保持装置の型取り並びに仮合せは、必要に応じて専門医の指導
のもとに実施すること。
第4 給付の決定等
1 村長は、身体障害者若しくは身体障害児について、更生相談所等の判定若しくは指
定育成医療機関等の医師の意見書又は医学的判定を要しないものについての検討結果
に基づいて、補装具の給付を決定したときは、それぞれ「補装具交付・修理券」(様
式第4号)又は「身体障害児補装具交付・修理券」(様式第7号)を速やかに交付す
ると同時に「補装具交付・修理委託(依頼)書」(様式第5号)又は「児童福祉法に
よる補装具交付・修理委託(依頼)書」(様式第8号)を補装具製作(修理)委託業
者に送付すること。
また、その申請を却下することを決定したときは、「却下決定通知書」(様式第12
号)を申請者に交付すること。
なお、身体障害者・児が更生相談所等の判定を受けた場合には、その結果を「措置
結果報告書」(様式第13号)により更生相談所等に報告するものとする。
2 補装具の価格は告示によることとし、身障法第38条及び児福法第56条に規定する本
人又は扶養義務者の負担すべき費用の額は「更生医療の給付又は補装具の交付若しく
は修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71
号局長通知)によること。
第5 適合判定
1 更生相談所等の判定又は指定育成医療機関並びに保健所の医師の意見書に基づいて
製作若しくは修理された補装具を給付するときは、第3に準じて更生相談所等による
適合判定を受けること。
なお、指定育成医療機関又は保健所の医師が行う場合は、必要に応じて更生相談所
に助言を求めること。
2 適合判定を行う際は、補装具の給付を受ける者、医師、補装具製作技術者、補装具
担当村職員及び身体障害者福祉司等の関係者の立ち会いのもとに実施すること。
3 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適しないと認められた場合は、製作業者に
対し不備な箇所を指摘し改善させた後給付すること。
4 生理的又は病理的変化により生じた不適合、申請者本人の過失による破損、取扱不
良のために生じた不適合等を除き、給付後9か月以内に生じた破損、不適合は、製作
業者の責任において改善させること。
第6 一括交付の取扱い
村長は、補聴器用電池、人工喉頭用電池、断端袋及び歩行補助つえ用先ゴムは補装具
修理券をもって、次により一括交付することができる。
この場合、身障法第38条及び児福法第56条の規定による費用徴収に係る負担能力の認
定は、補装具交付券又は補装具修理券1枚に記載された数量に相当する費用額について
行うこと。
(1) 補聴器用電池
ア 年間に必要とされる基準数は、標準型の場合は乾電池24個、高度難聴用の場合
は乾電池であれば36個、空気電池であれば30個までであること。
イ 一括交付数の限度は、乾電池であれば12個、空気電池であれば15個までである
こと。
ウ 補装具修理券は、乾電池であれば1枚につき4個、空気電池であれば1枚につ
き5個を記載し、申請1回につき3枚まで一括交付できること。
(2) 人工喉頭用電池
ア 年間に必要とされる基準数は、乾電池であれば16個、蓄電池であれば2個まで
であること。
イ 一括交付数の限度は、乾電池の場合8個までであること。
ウ 補装具修理券は、乾電池の場合、1枚につき4個を記載して、申請1回につき
2枚まで一括交付できること。
なお、蓄電池に係る補装具修理券の取扱については、1枚につき1個を記載す
るとともに、申請1回につき1枚とすること。
(3) 断端袋
年間に必要とされる基準数は、義手用4枚、義足用6枚であるが、これを補装具
修理券1枚により交付することができる。
(4) 歩行補助つえ用先ゴム
ア 職業の種類、歩行補助つえの利用状況等を勘案して6か月分を限度として必要
最低限の個数を、補装具修理券1枚により交付することができる。
イ 補装具修理券は、申請1回につき2枚まで一括交付できること。
第7 費用の徴収
村長は身障法第38条第2項又は児福法第56条第2項の規定により、当該身体障害者若
しくは身体障害児又はその扶養義務者から、その負担能力に応じた費用を徴収する場合
は、補装具給付後1か月以内に納入告知書を発行して徴収すること。
第8 関係帳簿
補装具の交付又は修理に当たっては、「補装具交付・修理申請処理簿」(様式第14号)
を備え、必要事項を記載しておくこと。
第9 補則
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされ
た処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについ
ては、なお従前の例による。
別紙(第1関係)
契約書(案)
身体障害者福祉法第20条及び児童福祉法第21条の6の規定に基づく補装具の製作及び
修理の委託について、川上村長(以下「甲」という。)と補装具製作業者(以下「乙」
という。)との間に、次の条項により契約を締結する。
第1条 乙は、甲が身体障害者及び身体障害児(以下「丙」という。)に対して交付し
た補装具交付・修理券(以下「補装具交付券」という。)による補装具の製作又は修
理を引き受けるものとする。
第2条 甲は、補装具交付券を丙に交付したときは、乙に対してその旨及びその必要な
事項を通知するものとする。
第3条 乙は、甲の発行する補装具交付券を所持する丙の補装具を製作又は修理しなけ
ればならない。
2 乙は補装具交付券の呈示を受けたときは、その処方に基づき、速やかに補装具を製
作又は修理し、当該補装具を丙に引き渡すものとする。
3 前項の引き渡しに当たり、特に甲の指定するときは、乙は、当該補装具に関する身
体障害者更生相談所又は指定育成医療機関若しくは保健所の医師の適合判定・検査を
経た後でなければ、これを交付してはならない。
第4条 乙は、丙に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
第5条 甲が乙に対して製作又は修理を委託する報酬の額は、補装具の種目、受託報酬
の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号及び同第187号)の別表に定める範
囲内とする。
第6条 乙は、丙に製作又は修理した補装具を引き渡す際に、補装具交付券に丙に対す
る支払うべき額が記載されているときは、丙にその支払を求めなければならない。た
だし、丙がその額の全部又は一部を支払わなかった場合においても、補装具の引き渡
しを拒んではならない。
第7条 乙は、甲に対して製作又は修理の代金を請求するときには、補装具交付券に丙
の受領印を受け、これを請求書に添付して請求しなければならない。この場合におい
て、丙が支払うべき額の全部又は一部を支払っていないときは、その旨及びその額を
請求書に記載しなければならない。
第8条 甲は、前条の規定に基づく請求書を受理したときは、製作又は修理の金額を照
査のうえ、その都度乙に支払わなければならない。
第9条 乙は、この契約による帳簿及び関係書類を5か年間保存しなければならない。
第10条 甲は、乙に対して、この契約の実施に関して必要な報告を徴し、又は説明を求
めることができる。
第11条 第3条第3項による適合判定の結果、その補装具が丙に適合しないと認められ
たときは、乙は甲の指示に従い、適合するまで乙の負担においてこれを改修しなけれ
ばならない。
2 甲は、補装具の交付後、身体障害者更生相談所又は指定育成医療機関若しくは保健
所の医師の行った適合判定・検査によって、乙の責任に帰すべきものと認められる不
備な箇所を発見したときは、前に準じて改修させることができる。
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときには、乙に対して一方
的にこの契約を取り消すことができる。
(1) 乙について、この契約の履行に監視、不正行為があったと認められるとき
(2) この契約の条項に違反があったとき
第13条 この契約書の有効期限は、 年4月1日から1年間とする。
2 この契約の有効期限の終了1か月前までに契約当事者のいずれか一方より何等かの
意思表示のないときは、契約の終期の翌日において向こう1か年間順次契約を更新し
たものとみなす。
以上契約の締結を証するため、本所2通を作成し、双方署名捺印のうえ各自1通を所
持するものとする。
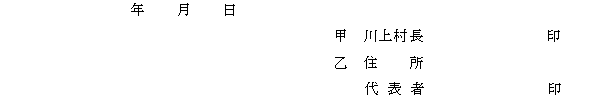 様式第1号
様式第1号
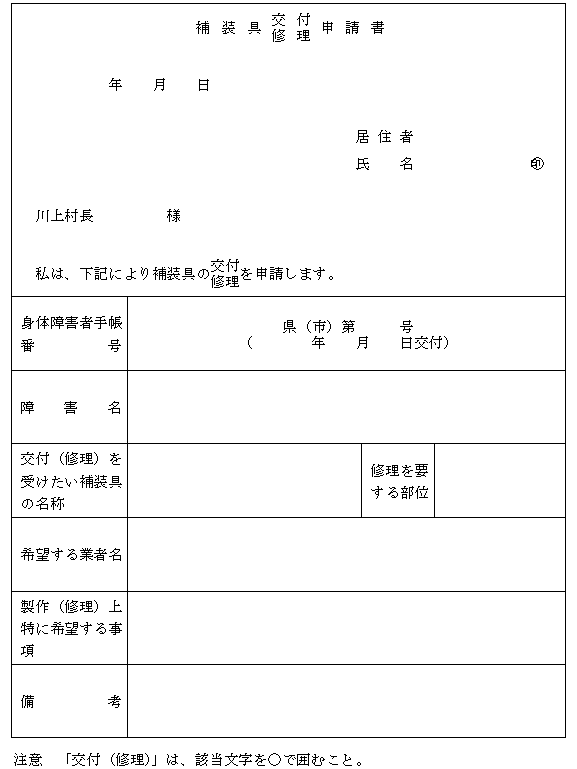 様式第2号
様式第2号
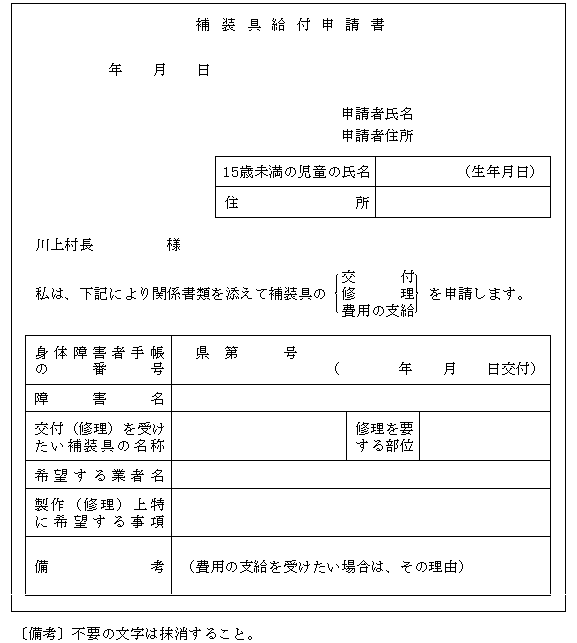 様式第3号
様式第3号
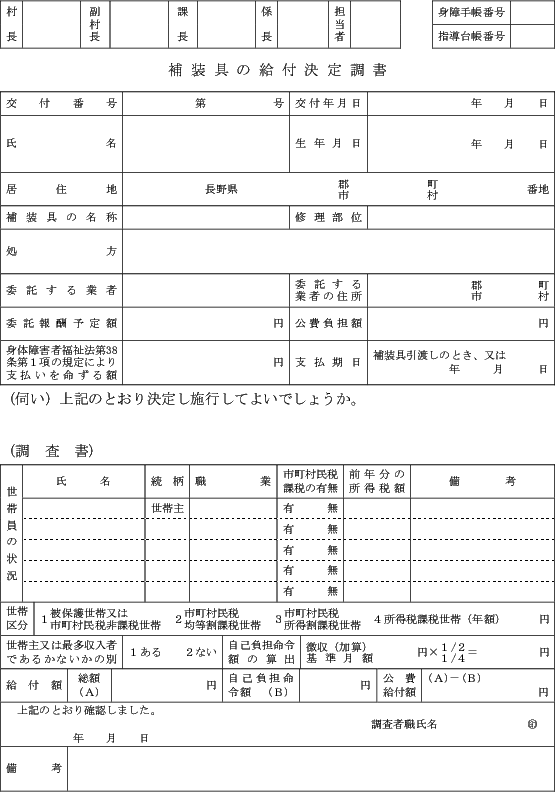 様式第4号
様式第4号
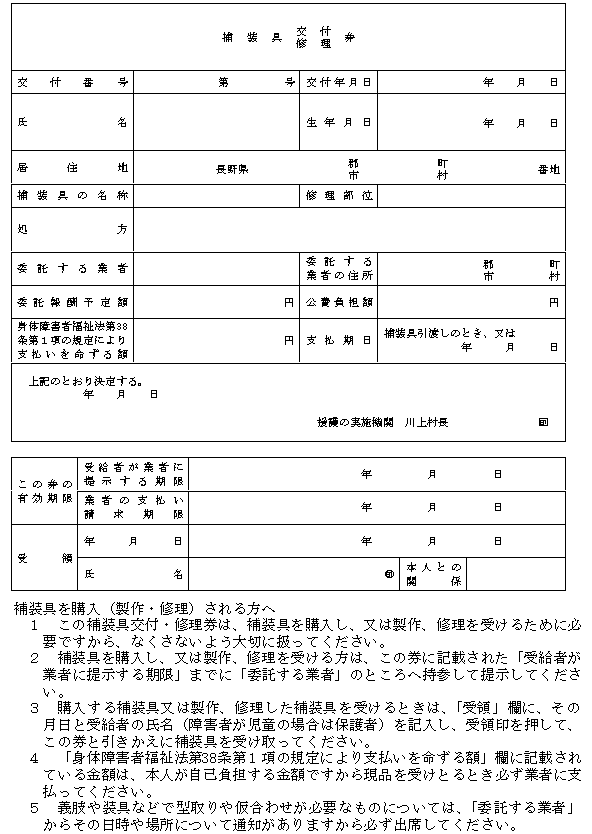 様式第5号
様式第5号
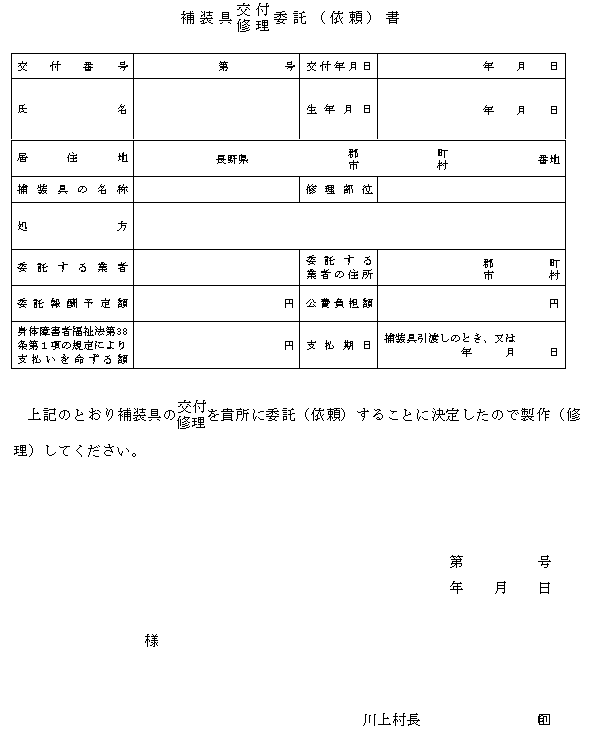 様式第6号
様式第6号
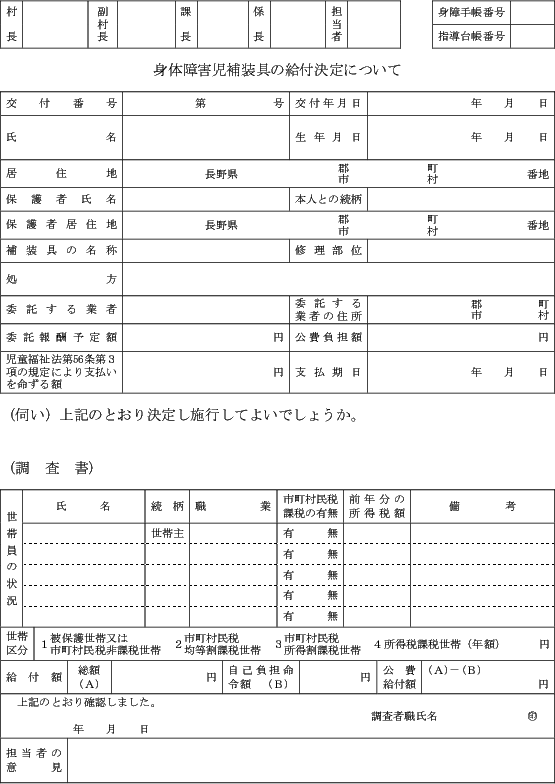 様式第7号
様式第7号
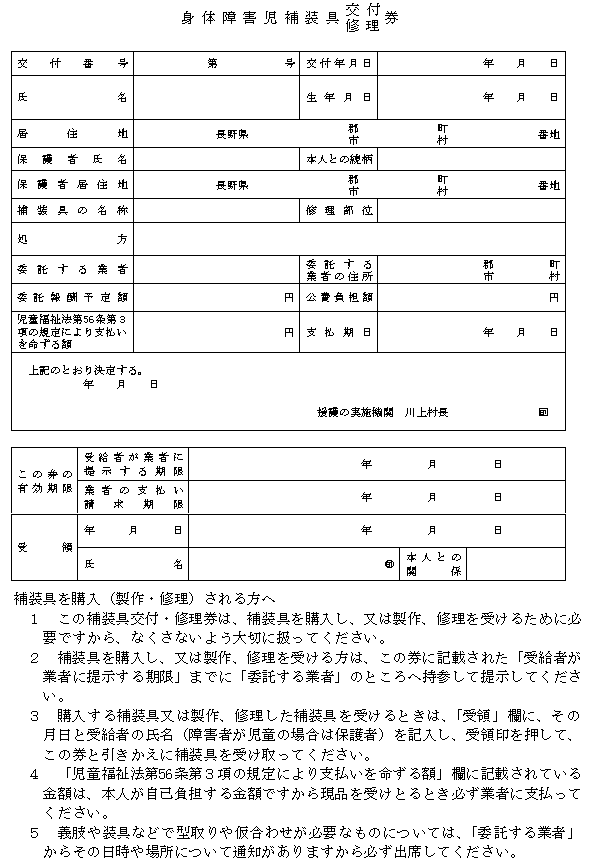 様式第8号
様式第8号
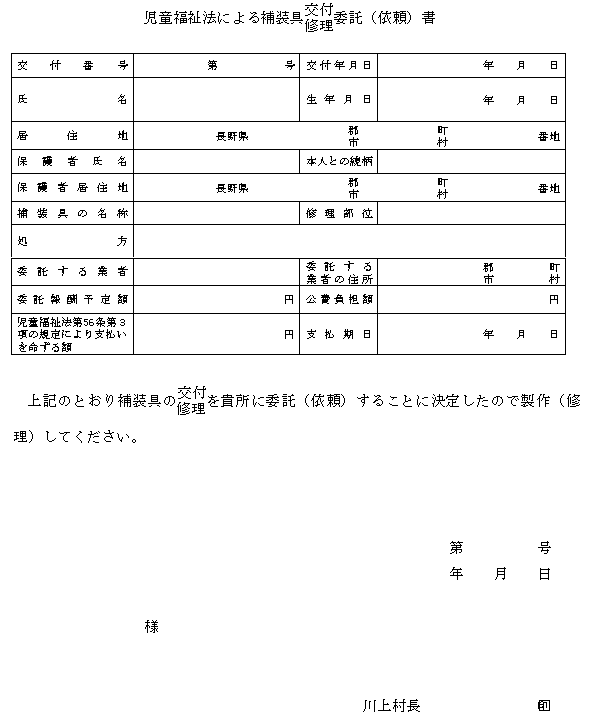 様式第9号
様式第9号
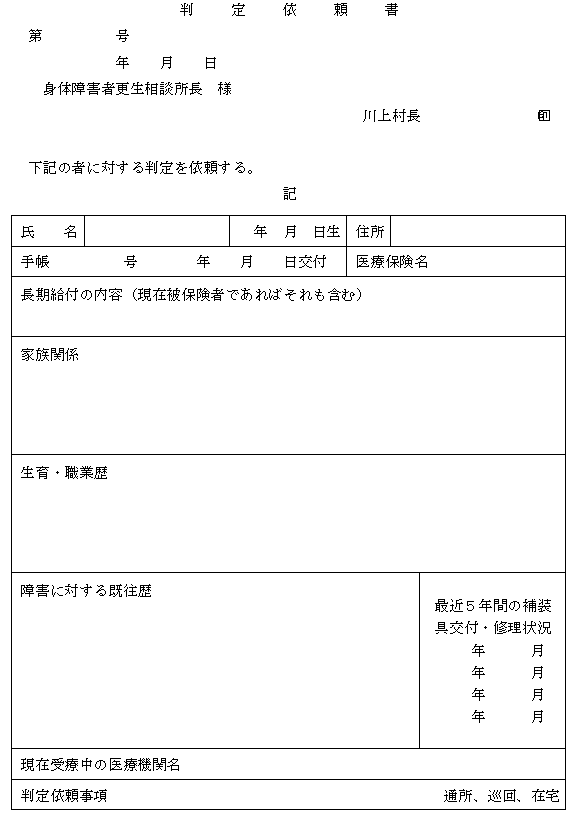 様式第10号
様式第10号
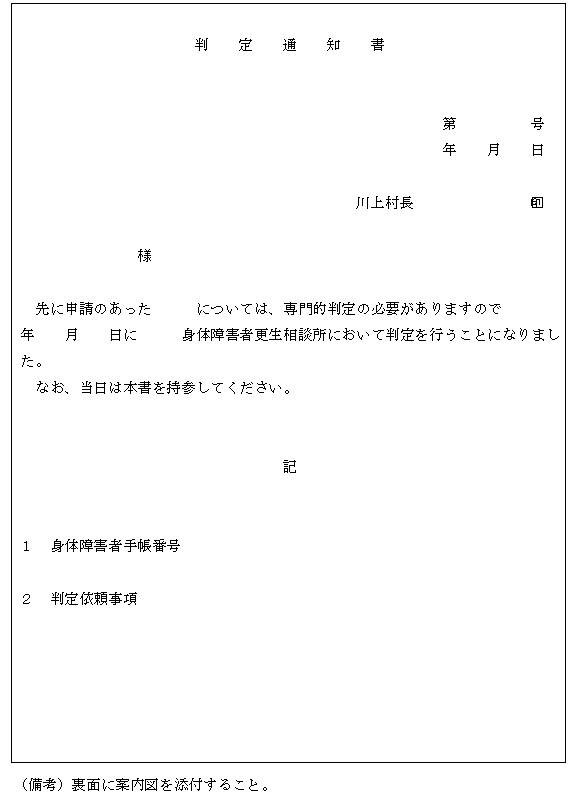 様式第11号
様式第11号
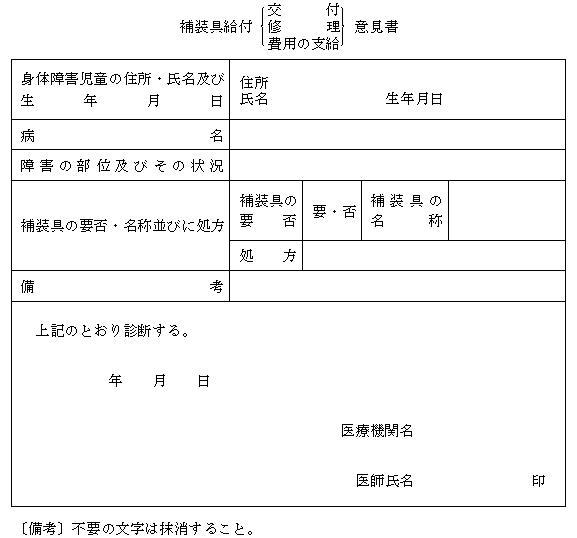 様式第12号
様式第12号
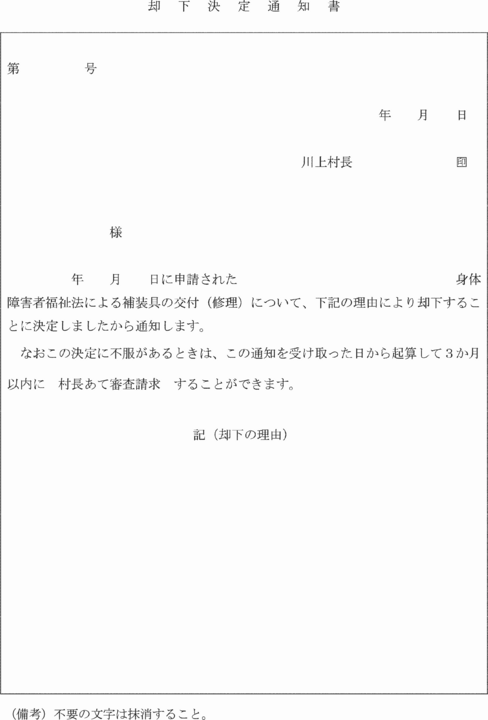 様式第13号
様式第13号
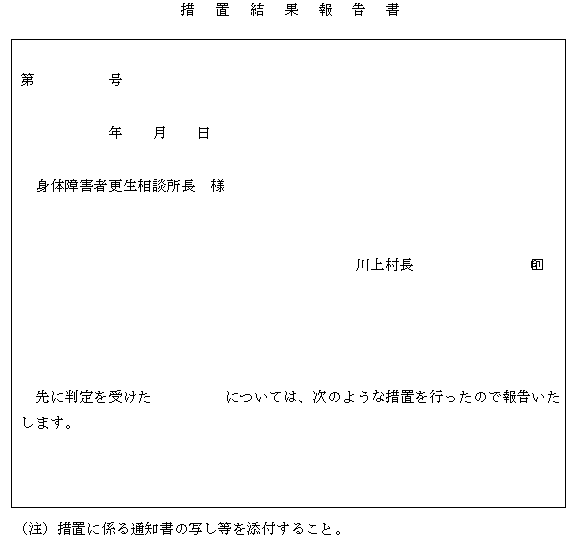 様式第14号
様式第14号

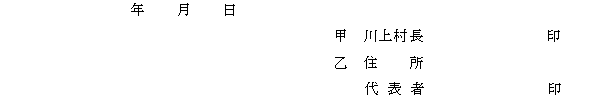 様式第1号
様式第1号
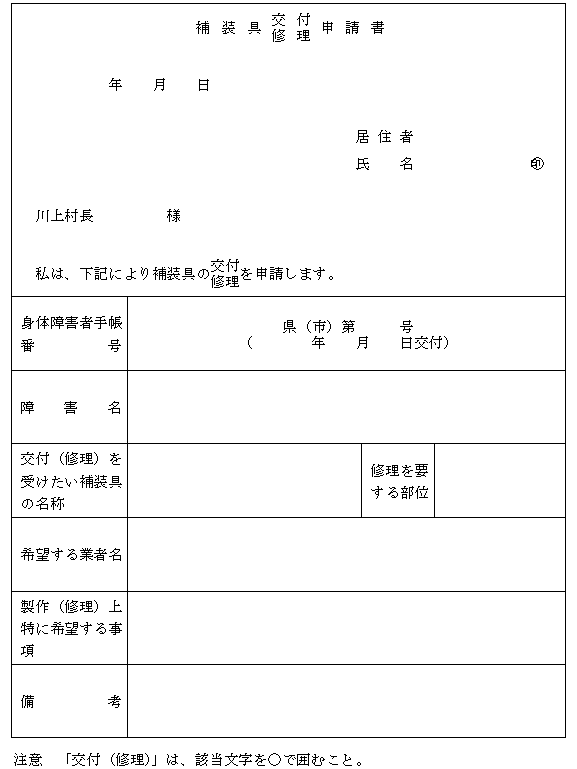 様式第2号
様式第2号
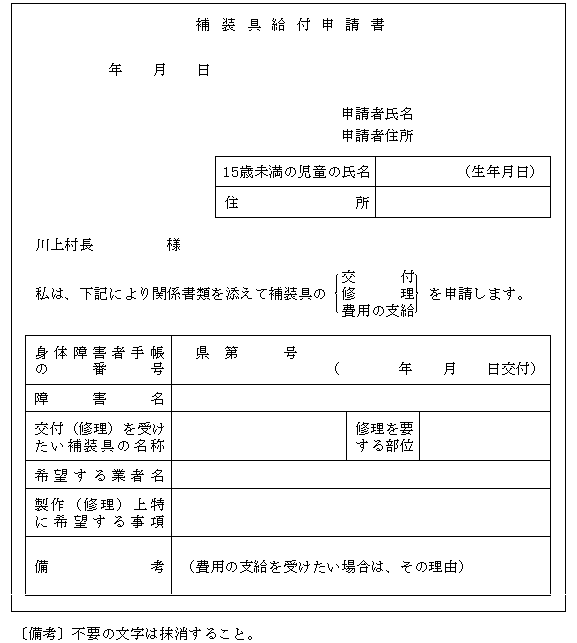 様式第3号
様式第3号
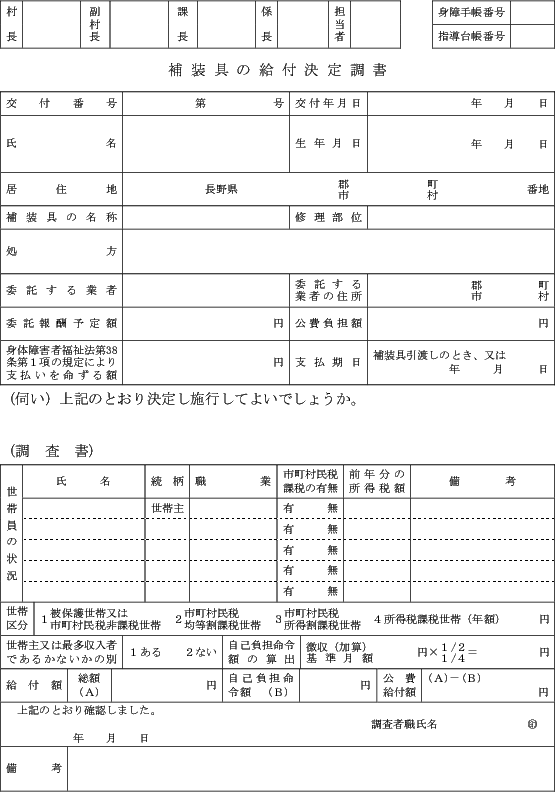 様式第4号
様式第4号
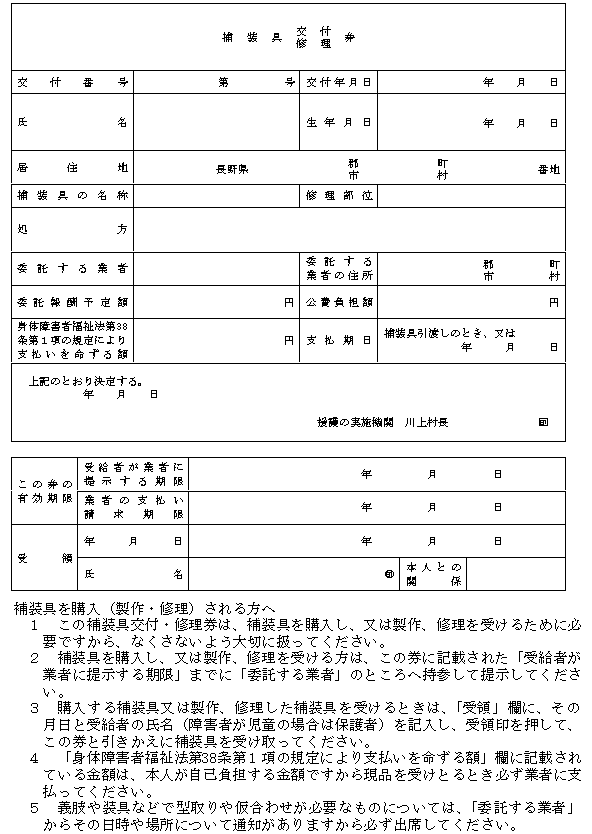 様式第5号
様式第5号
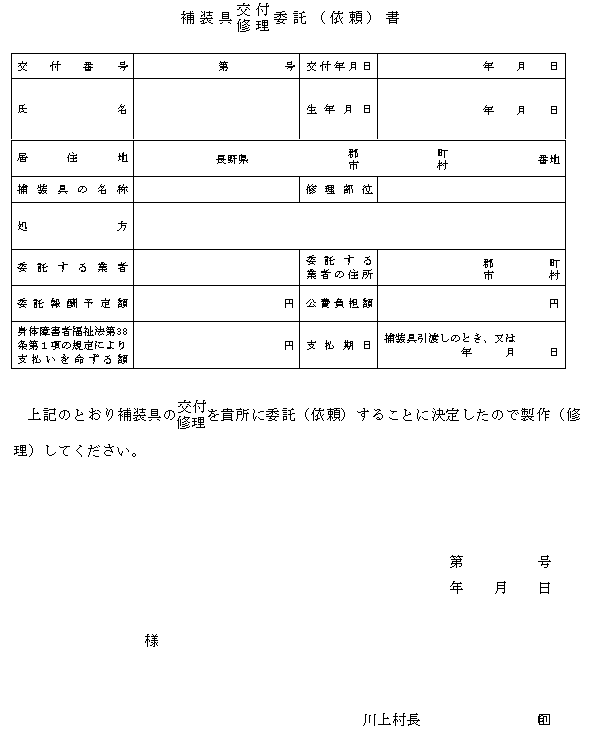 様式第6号
様式第6号
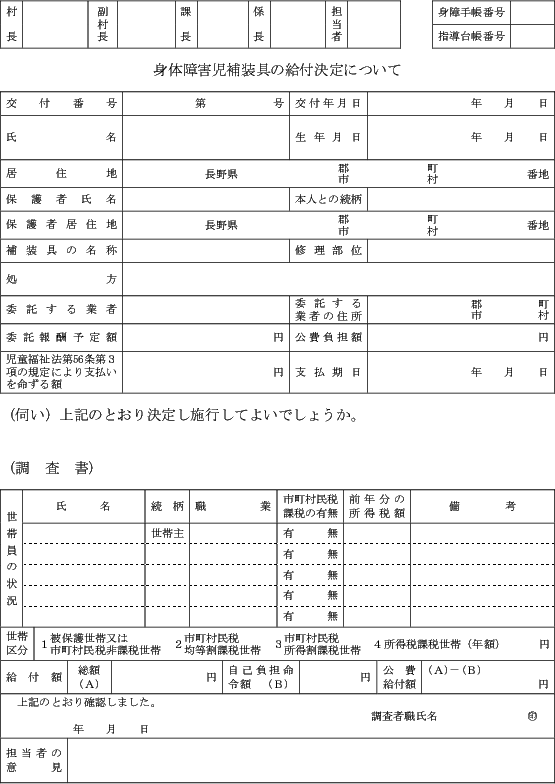 様式第7号
様式第7号
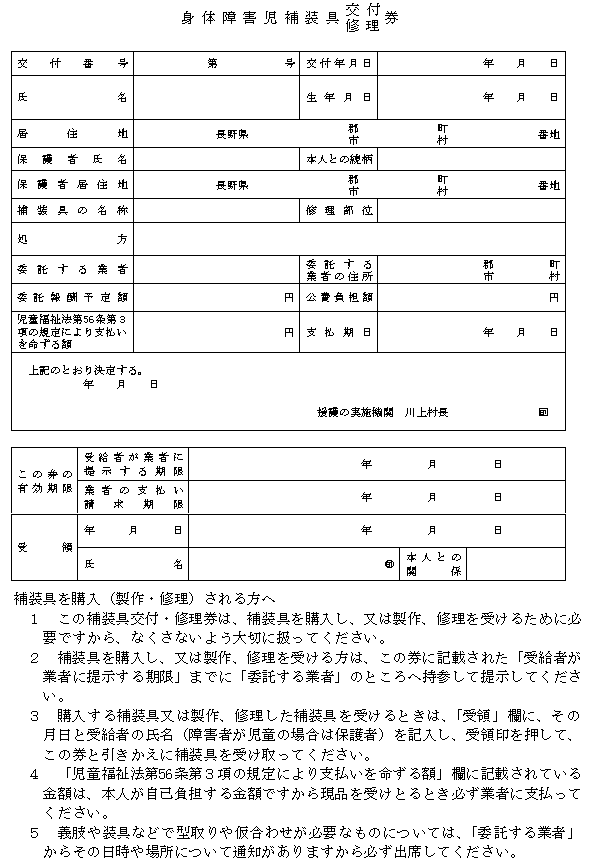 様式第8号
様式第8号
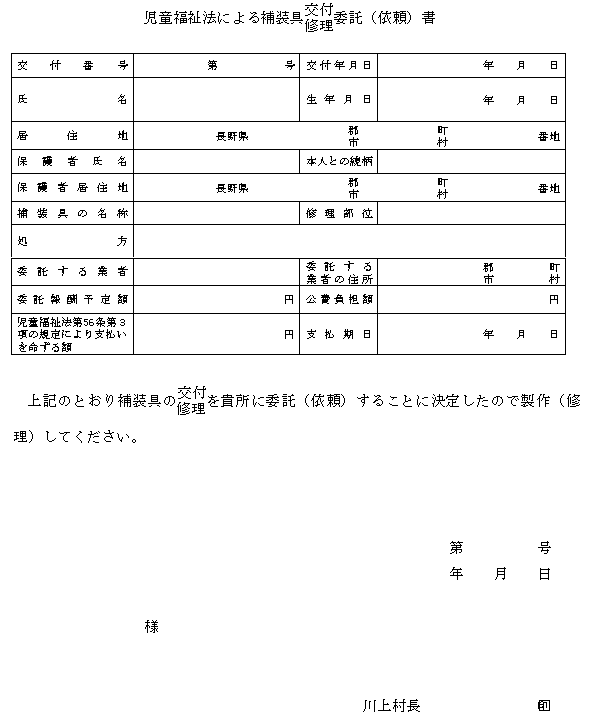 様式第9号
様式第9号
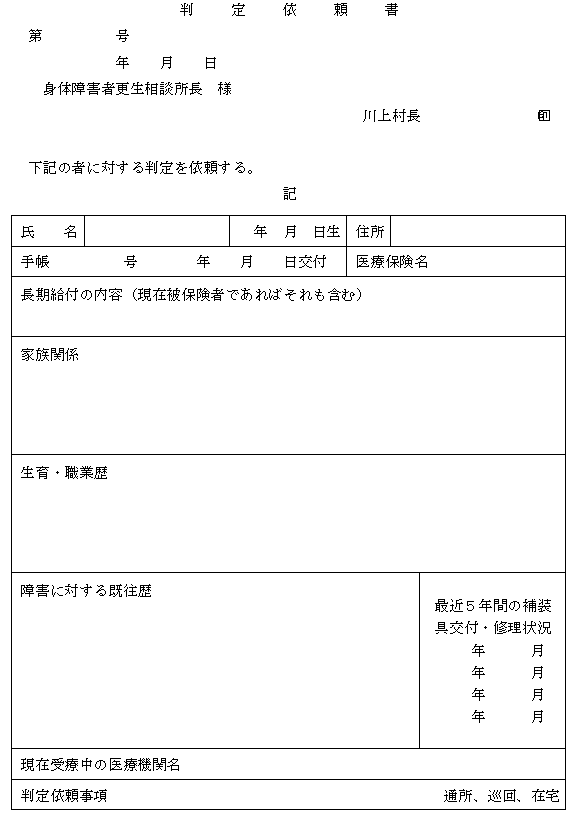 様式第10号
様式第10号
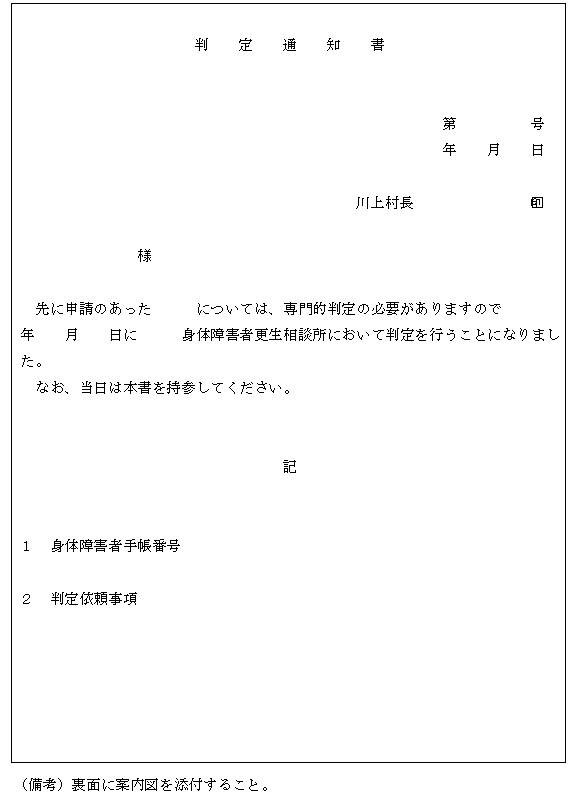 様式第11号
様式第11号
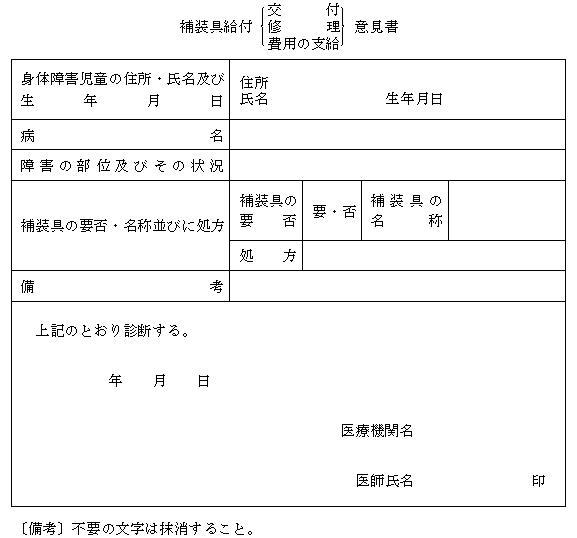 様式第12号
様式第12号
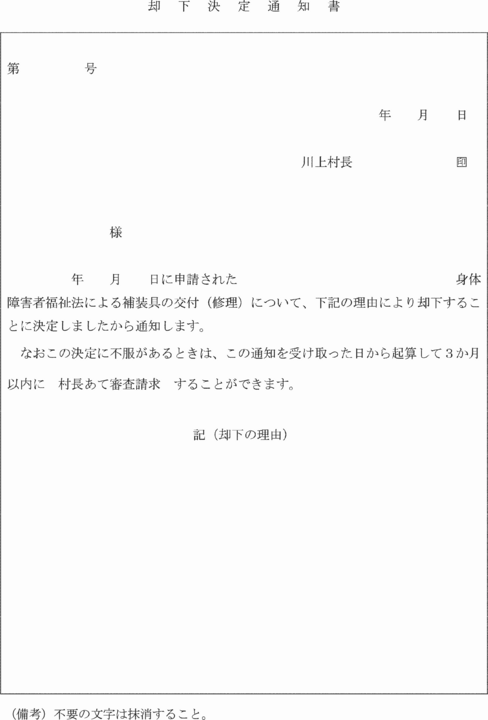 様式第13号
様式第13号
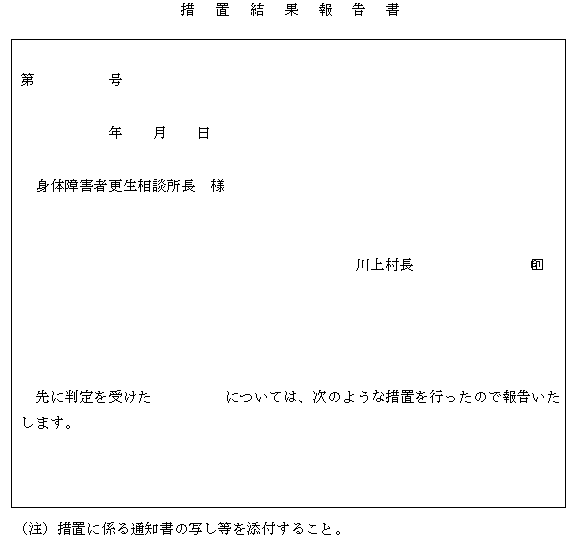 様式第14号
様式第14号

様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号