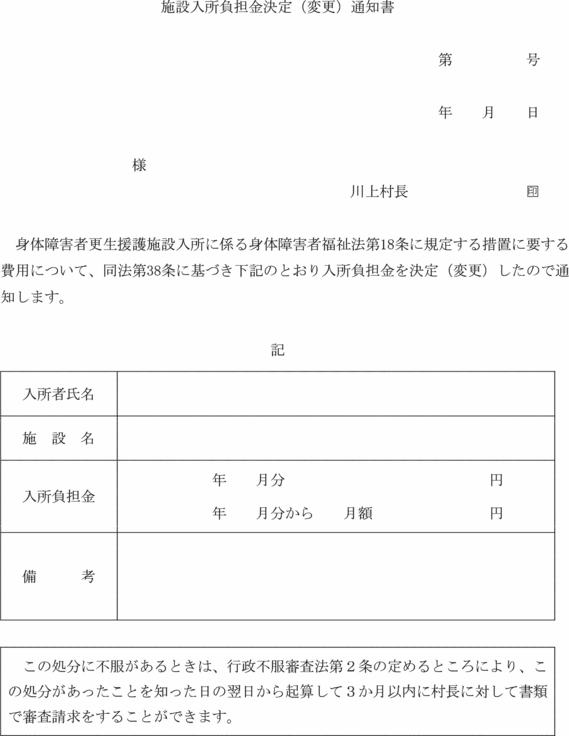○川上村身体障害者福祉法関係事務処理要領
平成5年3月31日要領
改正
平成13年3月16日要領第3号
平成13年3月30日要領第6号
平成19年3月26日要領第2号
平成28年3月17日告示第43号
川上村身体障害者福祉法関係事務処理要領
この要領は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体
障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉
法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)によるほか、法の施行に
ついて必要な事項を定めるものとする。
なお、事業の実施に当たっては、各事業の連携を図り、総合的な更生援護に努めるもの
とする。
第1 目的
この要領は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身
体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25
年厚生省令第15号。以下「省令」という。)によるほか、法の施行について必要な事項
を定めるものとする。
第2 更生医療給付事務関係
1 給付申請
村長は、身体障害者から更生医療給付申請書(省令別表第6号)の提出があったと
きは、更生医療給付申請処理簿(様式第1号。以下「申請処理簿」という。)に登載
するとともに、次の事項について内容を審査すること。
(1) 手帳が交付されている18歳以上の者であるか。
(2) 障害程度の認定の基礎となっている障害に必要な医療であるか。
2 給付の判定
申請の資格を有すると認められた者については、身体障害者更生相談所の長(長野
県身体障害者リハビリテーションセンター所長。以下「所長」という。)に対し、判
定依頼書(様式第2号)に更生医療給付の要否について指定医療機関の医師が作成し
た更生医療意見書(様式第3号)及び医療費概算額算定表(様式第4号)並びに身体
障害者診断書・意見書の写を添えて判定を求めること。
3 給付の決定
(1) 給付判定の結果により、給付が必要と認められた申請者に対する給付の決定は、
更生医療給付決定調書(様式第5号)により行うこと。
(2) 給付の期間が必要以上に及ぶことは、予算の効率的使用等の見地から厳に戒む
べきことであるので、入院期間が3月以上に及ぶものについての給付の決定に当た
っては特に慎重に取り扱うこと。
(3) 給付を決定したときは、申請者には更生医療券をもって決定通知に代えること
とし、給付を委託しようとする医療機関に対しては、更生医療委託通知書(様式第
6号)により通知すること。
(4) 判定の結果更生医療を必要としないと認められた者については、更生医療給付
申請却下通知書(様式第7号)により通知すること。
(5) 更生医療券の交付に当たっては次の事項に留意すること。
ア 入院により給付を受ける者には、病院・診療所用更生医療券(省令様式第8号
(1)。以下「病院用医療券」という。)のみを交付すること。
イ 通院により給付を受ける者には、病院用医療券及び薬局用更生医療券(省令様
式第8号(2)。以下「薬局用医療券」という。)の両方を交付すること。ただし、
病院、診療所に処方せんの交付を求めない旨申し出た者には、病院用医療券のみ
を交付すること。
ウ 入院して更生医療の給付を受けている者が退院し、その後引き続き通院による
更生医療の給付を受けるときは、前記イにより薬局用医療券を交付すること。
エ 更生医療券に記載する医療費概算額は、判定書に基づき記入することとし、有
効期限については、診療開始の時期等を考慮のうえ記入すること。
なお、医療費概算額には、装具代、移送費等村長が直接支給する概算額は含め
ないこと。
オ 給付を委託する医療機関の決定及び入院(通院)の時期については、更生医療
券の発行前に地理的条件及び申請者の希望等を考慮して決定すること。
カ 法第38条第1項の規定により支払を命ずる額(以下「自己負担額」という。)
について負担能力の認定を行った結果、医療費の一部を自己負担させることに決
定した者については、交付する更生医療券の自己負担額の欄に、各月ごとの自己
負担額と支払期限を記入すること。
この際、病院、診療所用更生医療券と薬局用医療券の両方を交付するときは、
病院、診療所用更生医療券のみに記入すること。
なお、自己負担額については、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修
理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71
号厚生省社会局長通知)によること。
キ 医療の具体的方針は、判定書に基づき詳細に記入すること。なお、更生医療券
の該当欄だけでは記入が困難なときは、別紙として添付しても差し支えないこと。
(6) 更生医療の給付の範囲は、更生医療券に記載されている医療に限られているこ
と。
4 医療の給付
(1) 医療の具体的方針の変更又は期間の延長について指定医療機関から承認を求め
られた村長は、更生医療期間延長・内容変更申請書(様式第8号。以下「変更申請
書」という。)の提出を求め、変更申請書に記載された内容について所長の意見を
徴して十分検討のうえ、変更又は延長が必要であると認められるものについては更
生医療期間延長・内容変更承認書(様式第9号。以下「変更承認書」という。)を
指定医療機関に通知すること。ただし、2週間以内の期間延長については、報告書
の記載に基づき所長の判定によらなくても、1回を限度として認められること。
(2) 変更又は延長を認めることができないときは、更生医療期間延長・内容変更不
承認通知書(様式第10号)により指定医療機関に通知すること。
5 医療費の支給
(1) 更生医療は指定医療機関に委託し現物給付によって行うことを原則としている
ので、給付に代えて費用を支給することはやむを得ない事情がある場合に限るもの
とすること。
(2) 付添看護
ア 付添看護を要する場合は、看護について特別の承認(基準看護の承認)を得て
いる指定医療機関に委託することとして付添看護料の支給はできるだけ避けるこ
と。
イ 付添看護を必要とする者には、更生医療費支給承認申請書(様式第11号)に更
生医療券を添えて申請させること。
ウ 付添看護料の申請書を受理した村長は、調査のうえ必要と認める者に対しては
更生医療費支給承認通知書(様式第12号)を、必要と認めない者に対しては更生
医療費支給却下通知書(様式第13号)をもって当該申請者に通知すること。
エ 家族が行う付添看護の経費は認められないこと。
オ 付添看護の経費を請求するときは、身体障害者更生医療費(施術、看護、移送、
治療材料)請求書(様式第14号。以下「医療費請求書」という。)に看護料請求
明細書(様式第15号)を添えて請求させること。
カ 看護料の算定は「生活保護法による付添看護料の支給基準」(昭和33年7月3
日社発第424号社会局長通知「医療扶助運営要領」)の例によること。
(3) 移送費
ア 移送費は本人を移送するために必要とする最小限度の経費とすること。
なお、家族が行った介護等の経費については認められないこと。
イ 移送費を必要とするときは、前記(2)のイ及びウに準じて取り扱うこと。
ウ 移送費を請求するときは、医療費請求書に移送費請求明細書(様式第16号)を
添えて申請させること。
エ 移送費の算定は、移送のために必要とする最小限度の実費とする。
(4) 施術費
ア 施術はマッサージのみを認めるものとし、給付は原則として指定医療機関内で
医師の診断指導のもとに行うものである。ただし、マッサージ師のいない指定医
療機関にあっては、担当の医師の処方に基づいてその指定する施術所において施
術を受ける場合に限り認めること。
イ 施術費を必要とするときは、前記(2)のイ及びウに準じて取り扱うこと。
ウ 施術費を請求するときは、医療費請求書により申請させること。
エ 施術料は健康保険診療報酬点数表(乙)により算定すること。
(5) 治療材料費
ア 治療材料費は治療経過中に必要と認められた最小限度の材料及び治療装具のみ
を支給すること。
なお、この場合は現物支給することができること。また、運動療法に要する器
具は指定医療機関において整備されておるものであるから、支給は認められない
こと。
イ 治療材料費の算定に当たっては、その実費とすること。
(6) 更生医療の給付に当たり手術実施退院後医学的措置を必要とし、かつ、指定医
療機関に通院することが困難である場合は、当該指定医療機関の処方により本人の
近辺の専門医において給付を行うことは差し支えないこと。
なお、この場合は当該専門医が健康保険法(大正11年法律第70号)により採用し
ている健康保険診療報酬点数表により算定した請求書により、その医療費を本人に
支給すること。
6 指定医療機関における診療報酬の請求及び支払
(1) 診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付のうえ、当該医療
機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「基金
等」という。)に提出すること。
(2) 自己負担額については、指定医療機関が本人又は扶養義務者から徴収するもの
であるが、医療機関において徴収することができないときは、村長にその旨を報告
し、当月分の診療報酬請求額に含めて請求すること。
(3) 指定医療機関において徴収できない自己負担額の全部又は一部を本人又は扶養
義務者に代わって村において支払った場合には、その額を本人又は扶養義務者から
徴収すること。
7 更生医療給付決定簿等の整備
(1) 村長は、前記3の(1)による給付決定を行ったときは、申請処理簿に更生医療
券より該当欄に対応する項目を転記整理しておくこと。
(2) 連名簿により診療報酬の額について知事が決定したときは、更生医療診療報酬
決定簿(様式第17号)に記入すること。
第3 削除
第4 身体障害者更生援護施設入所委託事務
1 入所申請
(1) 身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)への入所(通所を含む。以
下同じ。)を希望する本人又は保護者(以下「申請者」という。)は、身体障害者
更生援護施設入所申請書(様式第24号。以下「申請書」という。)に必要事項を記
入し、健康診断書を添付の上、村長に提出すること。
(2) 村長は、入所申請等があったものについて、施設入所申出等処理簿(様式第25
号)に記入し、整理すること。
2 措置の決定等
(1) 村長は、施設入所が適当であるか十分検討し、入所が適当と認めたときは身体
障害者調査書(様式第26号)を作成するとともに、所長に対し、判定依頼書(様式
第2号)に身体障害者調査書を添付し、入所の適否の判定を依頼すること。
(2) 村長は、所長の判定に基づき入所の適否について審査し適当と認めたときは、
入所調整の結果を踏まえ、次の事項について措置決定調書(様式第27号)を作成の
上、措置決定を行うこと。
ア 入所委託の措置、措置解除及び措置変更(施設等)を決定したときは、申請者
に対し措置決定通知書(様式第28号)により通知すること。
イ 所長の判定等に基づき、入所措置が適当でないと認められたときは、申請者に
対して入所申請却下通知書(様式第29号)により通知すること。
3 援護委託等
(1) 村長は、2の(2)のアに定める入所委託の措置及び措置解除を決定したときは、
施設の長に対し援護委託(解除)決定通知書(様式第30号)により通知するととも
に、所長に対し措置結果報告書(様式第31号)により報告すること。
(2) 村長は、常に施設に援護委託した入所者の状況の把握に努め、施設長と協議の
上、必要に応じ補装具の交付、更生医療の給付、施設の変更等総合的な措置の実施
について所長の意見を求めること。
4 委託費の請求書等
(1) 法人等の代表者等(以下「代表者等」という。)は、当該月の委託に関する費
用について援護委託費概算払(精算)請求書(様式第32号)により、毎月5日まで
に村長に請求すること。
(2) 村長は、当該月の15日までに援護委託費の概算払を行うこと。
(3) 代表者等は、概算払を受けた委託費にあっては前月分を精算した援護委託費概
算払(精算)請求書を、更生訓練費にあっては前月分の実績により更生訓練費支給
申請書(様式第33号)をそれぞれ翌月の5日までに村長に提出すること。
(4) 村長は、援護委託費の支給状況を援護委託費支給台帳(様式第34号)により整
理しておくこと。
5 居住地を変更した場合の取り扱い
(1) 施設入所者の出身世帯が転居等により本村から転出し、居住地が他市町村(以
下「新居住地」という。)に移動する場合には、村長は、居住地変更通知書(様式
第35号)により新居住地の市町村長、施設長及び入所者に通知すること。
(2) 村長は、施設入所者の居住地が本村に移動した旨の通知を受けた場合には、居
住地変更通知書に基づき入所委託の措置決定を行い、措置決定通知書により施設長
及び入所者に通知すること。
(3) 新居住地の市町村への変更時期については、原則として月の初日現在で行われ
るよう、新居住地の市町村と連絡調整を図るものとすること。
6 措置の変更
村長は、措置の変更をしようとするときは、所長の判定を求め、所長の判定に基づ
き、入所中の施設の措置解除と変更後の施設の入所委託の措置決定を行うこと。
この場合、旧援護委託施設の長は、新援護委託施設の長に施設変更の関係書類引継
書(様式第36号)を送付するものとする。
7 遺留金品の取り扱い
(1) 施設入所者が死亡した場合には、施設長はその入所者の葬祭・遺留金品状況届
書(様式第37号)を村長に提出すること。
(2) 村長は、相続人に対し遺留金品の処分方法を確認の上、遺留金品処分指示書(
様式第38号)により、施設長に遺留金品の処分方法を指示すること。
(3) 相続人が明確な場合には、施設長は、村長の立会いのもと、遺留金品を相続人
の代表者に引渡し、遺留金品受領書(様式第39号)を徴収すること。
(4) 相続人が不明確な場合で、遺族等又は施設が利害関係人として、あるいは検察
官が民法(明治29年法律第89号)上の所定の手続きを取ることが困難な場合には、
被措置者があらかじめ定めておいた親族等の代表者又はその代理人に対して遺留金
品の引渡しができるものとすること。
(5) 7の(3)、(4)のいずれの処分もできない場合には、村長は家庭裁判所に対し、
民法第952条の規定による相続財産管理人の選任請求を行うものとすること。
(6) 遺留金品の処分が終了した場合には、施設長は村長に葬祭・遺留金品処理状況
報告書(様式第40号)を提出すること。
8 入所委託費の支弁額
入所に要する委託費の支弁額は、当該年度の身体障害者保護費国庫負担(補助)金
交付要綱(昭和62年厚生省厚生事務次官通知厚生省社第529号)に定めるところによ
ること。
9 その他
施設長は、入所者の身上に重大な事故等が生じたときは、事故等報告書(様式第41
号)により、村長及び県障害福祉課長に報告すること。
第5 身体障害者更生援護施設入所負担金徴収事務
1 費用負担能力の認定等
村長は、費用負担能力の更新をしようとするときは、費用負担能力認定調書(様式
第42号及び第43号)を作成の上、負担金の額を決定し、施設入所負担金決定(変更)
通知書(様式第44号)により被措置者又は被措置者の扶養義務者に通知すること。
2 費用負担能力の更新
(1) 費用負担能力の認定の更新は、毎年7月1日に行うこと。
(2) 前号の規定にかかわらず、年の中途において、費用負担能力に著しい変動があ
ったときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の
属する月)から認定を更新すること。
3 負担金の額の決定
(1) 負担金の額の決定は、身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関
する規則(平成5年規則第5号)に規定する徴収月額により行うこと。
(2) 費用負担者の災害、疾病、その他やむを得ない事由により前項による負担金を
徴することが著しく不適当であると認めるときは、村長が別に定める額とすること。
(3) 負担金の額の決定に当たり、所得税額を計算する場合においては、次の規定は
適用しないものとすること。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第
3項
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項
ウ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条
4 負担金の徴収
第1項に規定する措置に基づく負担金の徴収は、次によるものとすること。
(1) 村長は、毎月25日までに被措置者又はその扶養義務者に納入通知書(川上村財
務規則(昭和63年規則第2号)様式第51号)を発行するものとする。
(2) 村長は、前号にかかわらず、当該負担金の納入について、口座振替により納付
することをあらかじめ申し出た者については施設入所負担金納入通知書(様式省略)
を発行することができるものとすること。
(3) 村長は、徴収金が納期までに納入されないときは、督促状(様式省略)を発行
すること。
(4) 村長は、督促してもなお納入しない者に対しては、履行催告書(様式省略)を
発行すること。
附 則(平成13年3月16日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成13年3月30日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日要領第2号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされ
た処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについ
ては、なお従前の例による。
別紙 削除
様式第1号
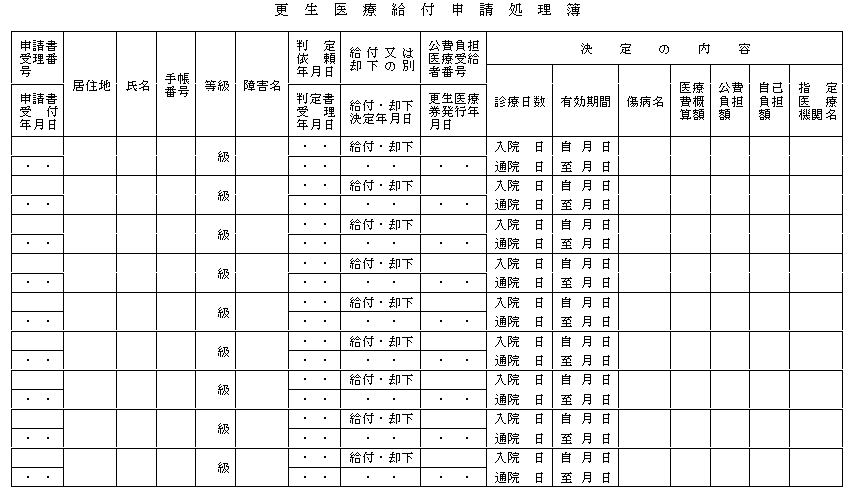 様式第2号
様式第2号
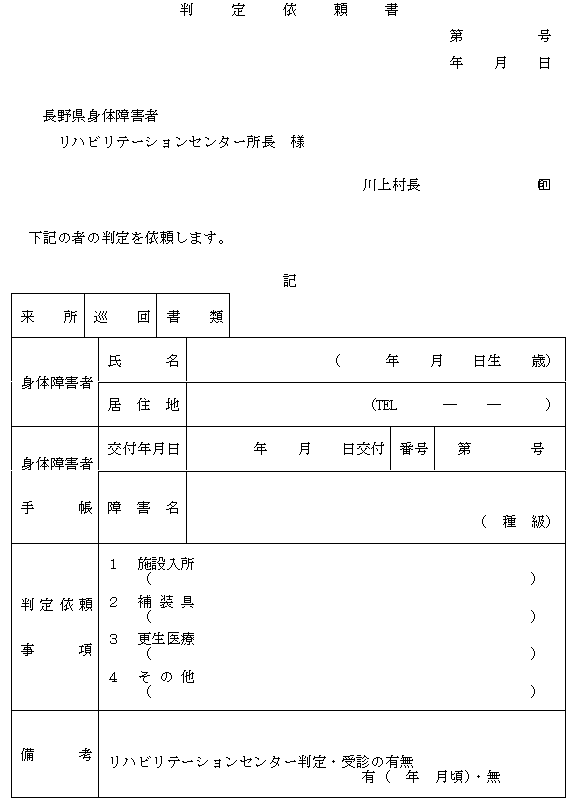 様式第3号
様式第3号
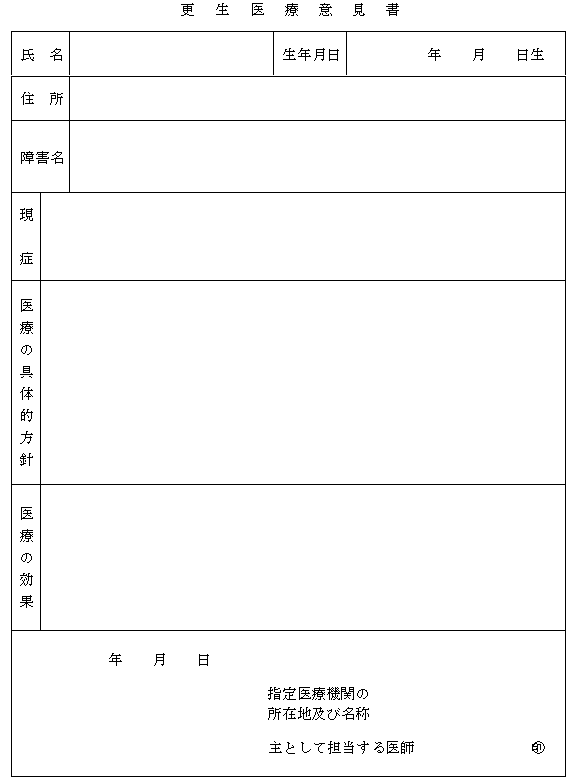 様式第4号
様式第4号
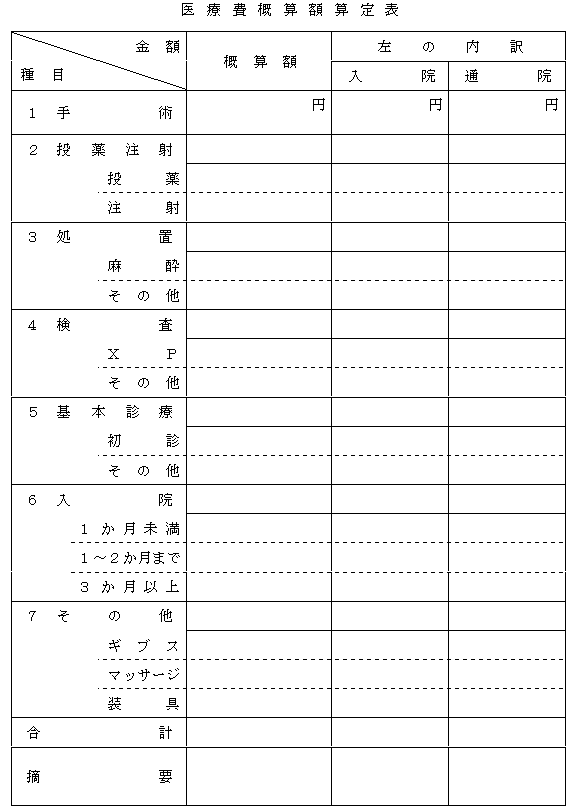 様式第5号
様式第5号
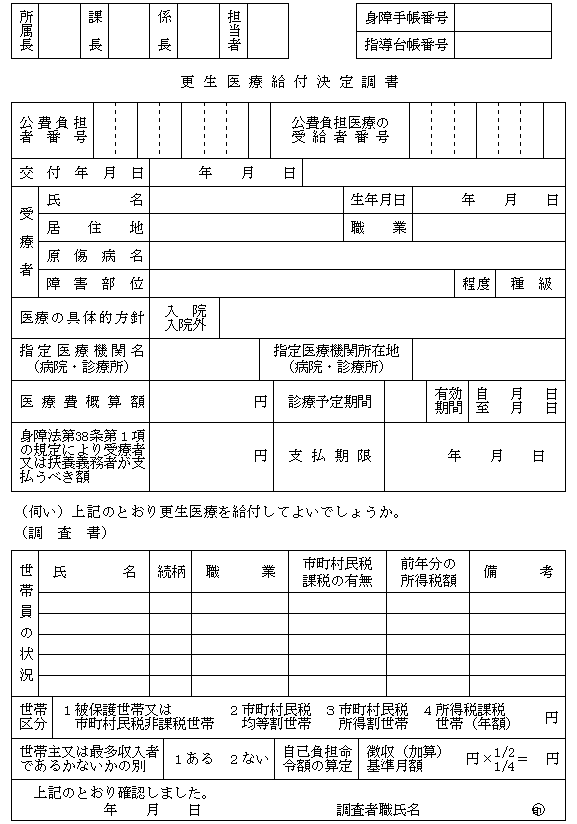 様式第6号
様式第6号
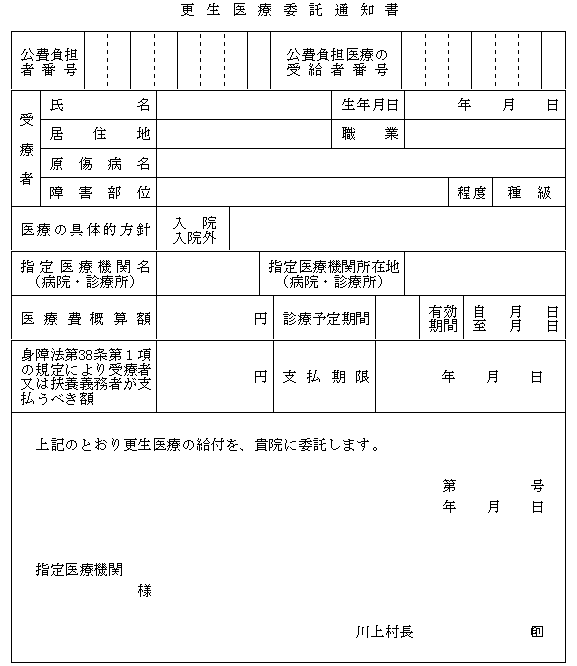 様式第7号
様式第7号
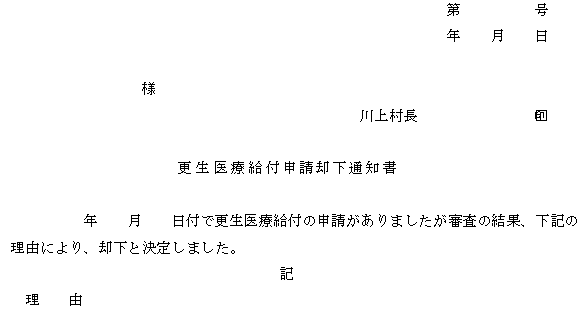 様式第8号
様式第8号
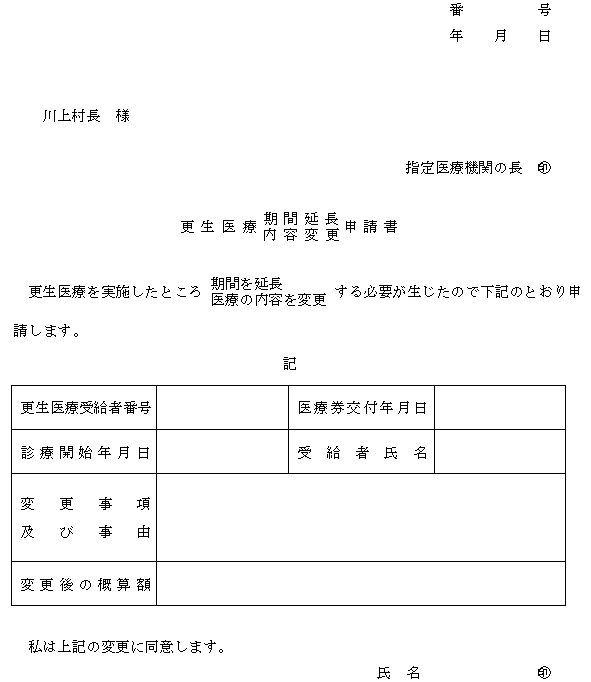 様式第9号
様式第9号
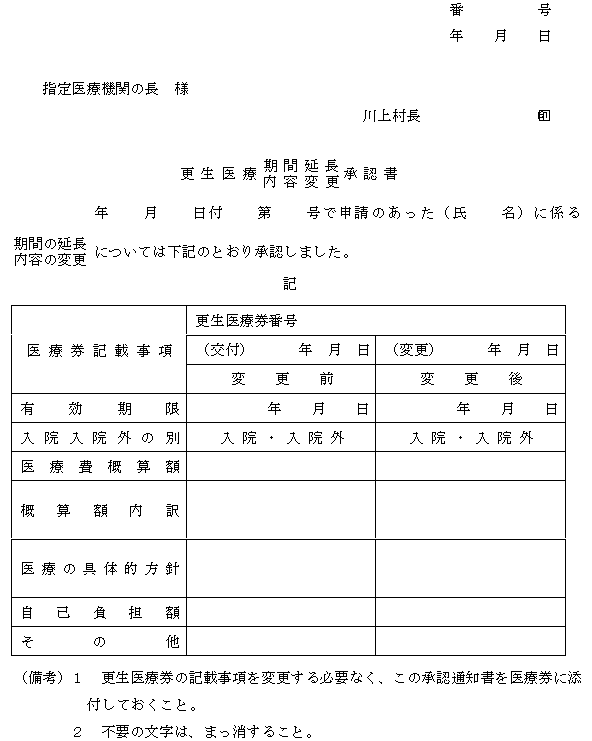 様式第10号
様式第10号
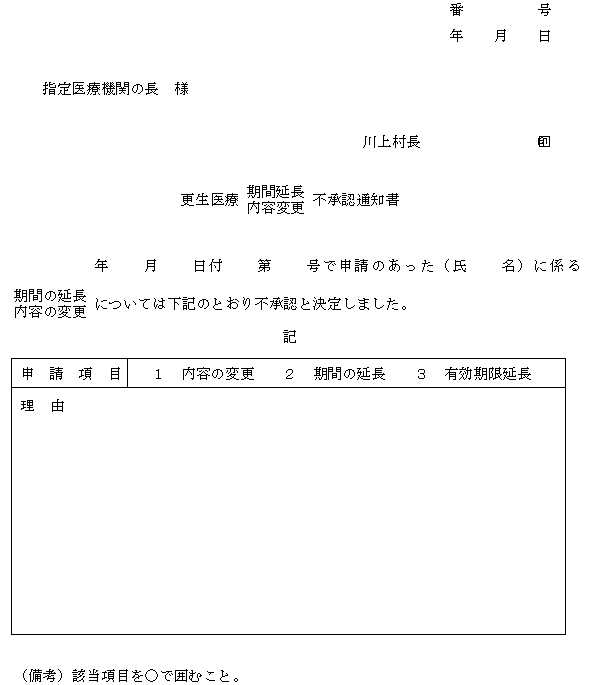 様式第11号
様式第11号
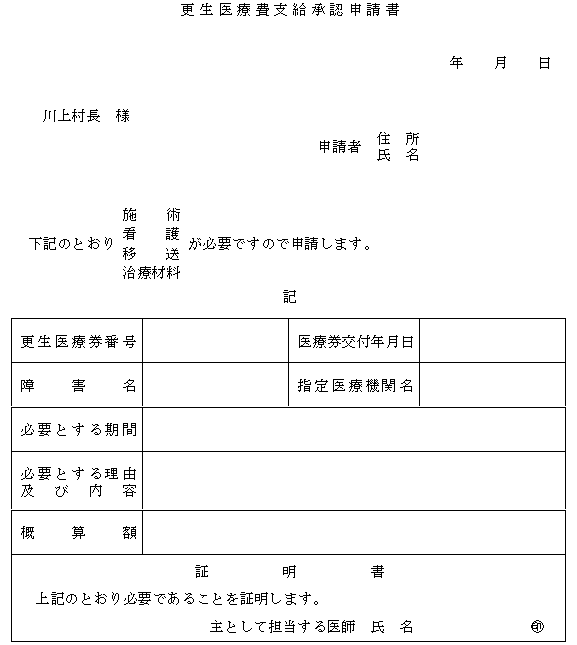 様式第12号
様式第12号
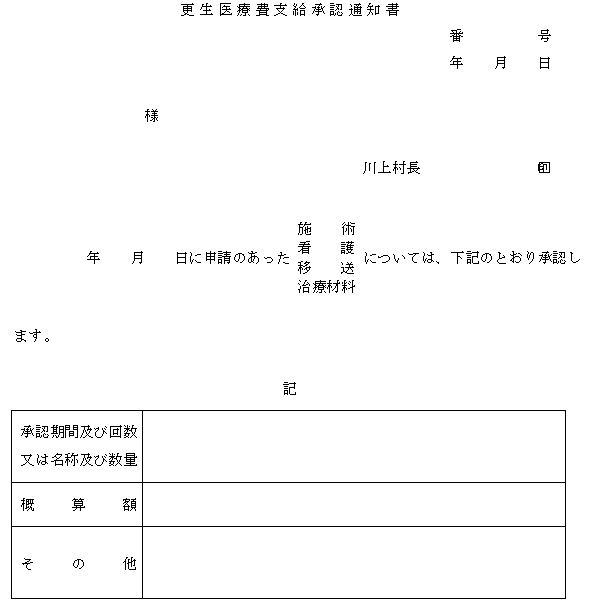 様式第13号
様式第13号
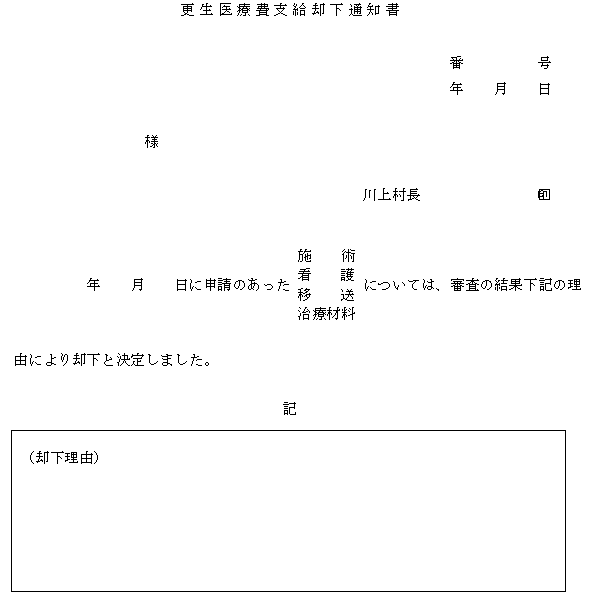 様式第14号
様式第14号
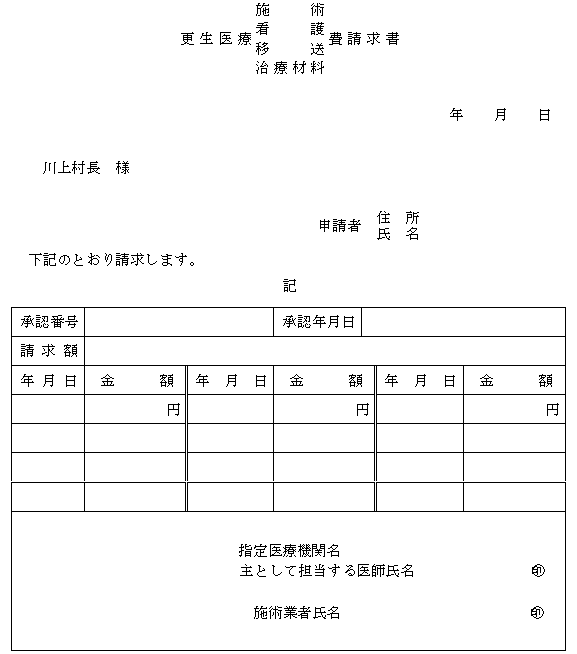 様式第15号
様式第15号
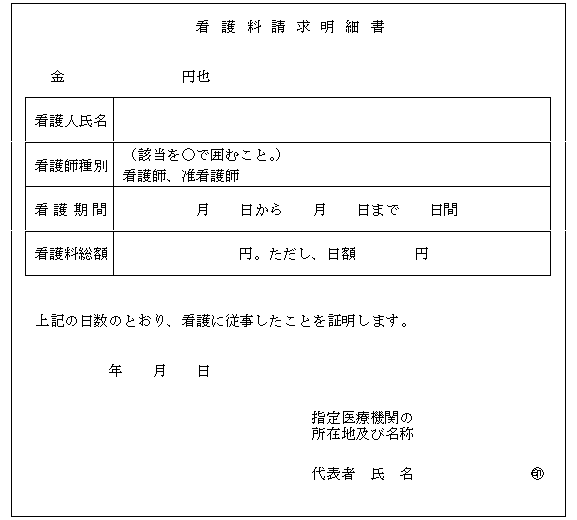 様式第16号
様式第16号
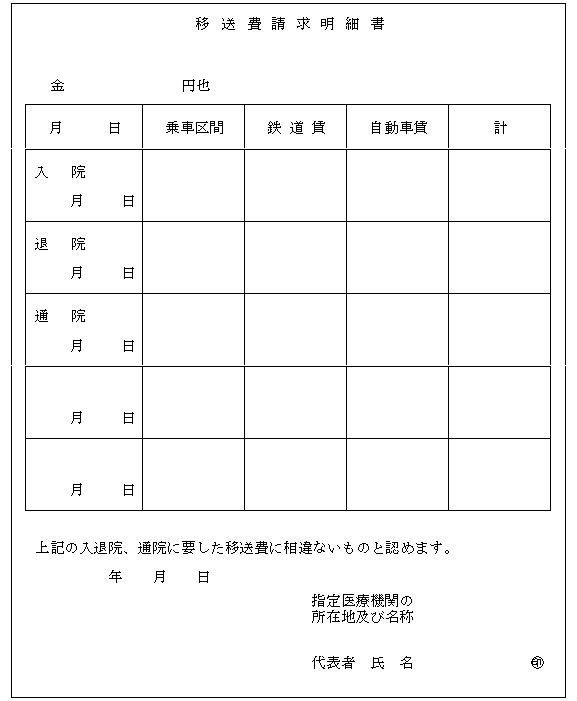 様式第17号
様式第17号
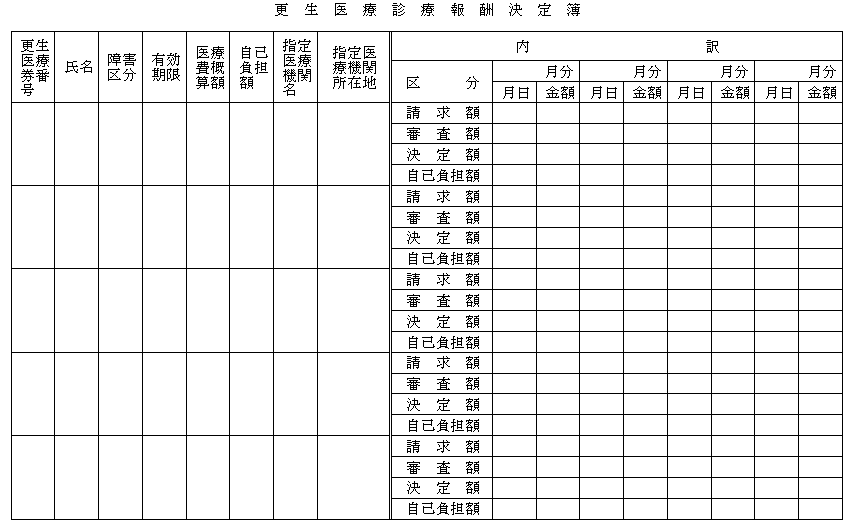 様式第18号から様式第23号まで 削除
様式第24号
様式第18号から様式第23号まで 削除
様式第24号
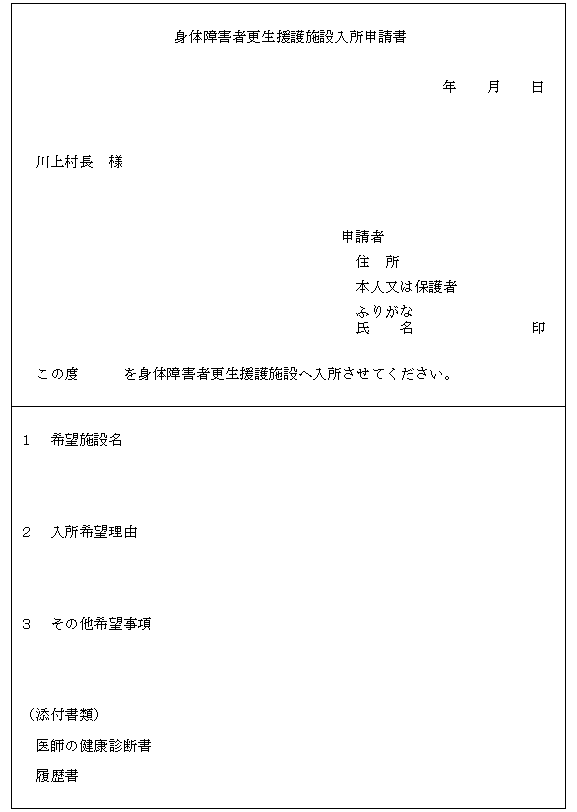 様式第25号
様式第25号
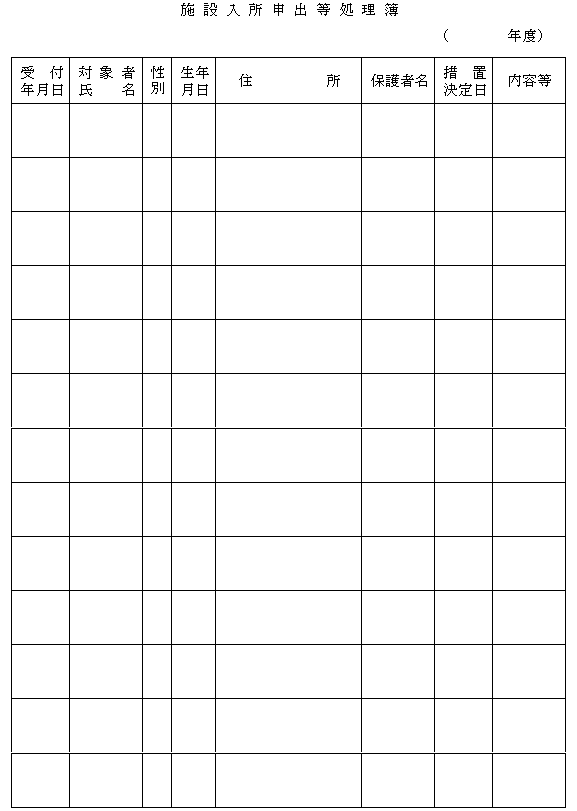 様式第26号
様式第26号
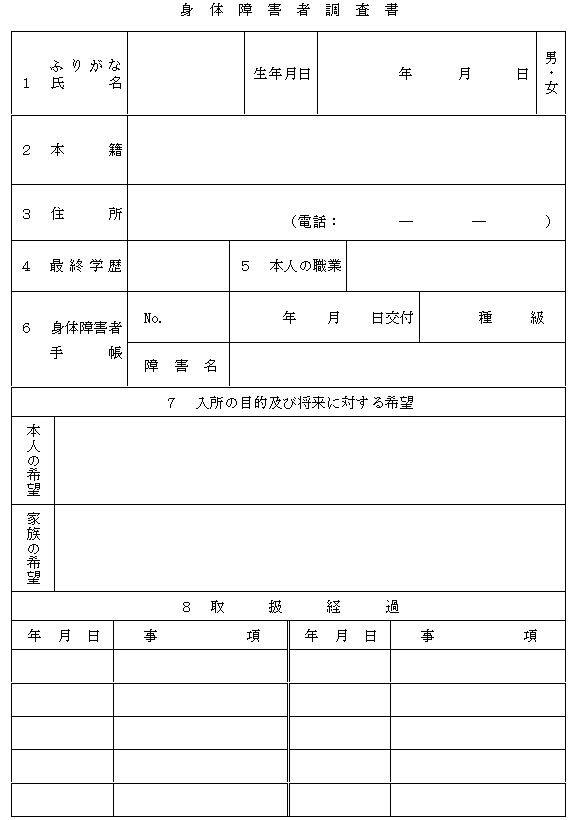
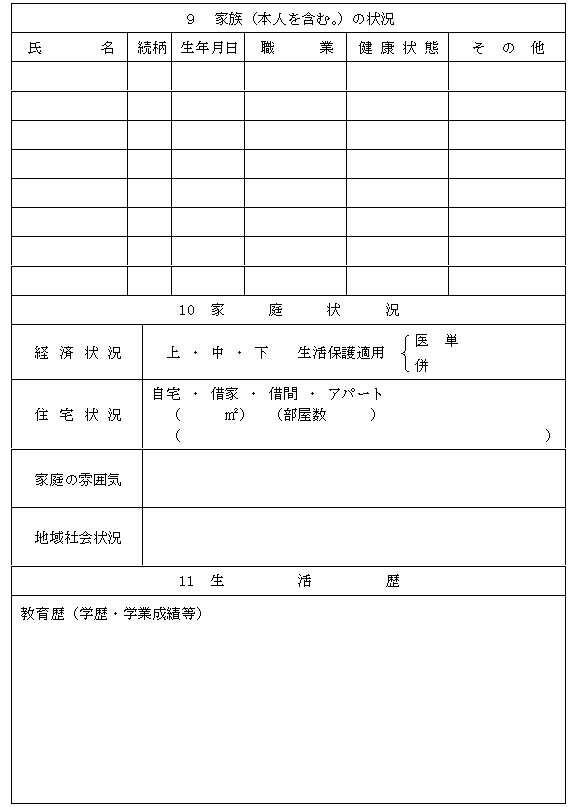
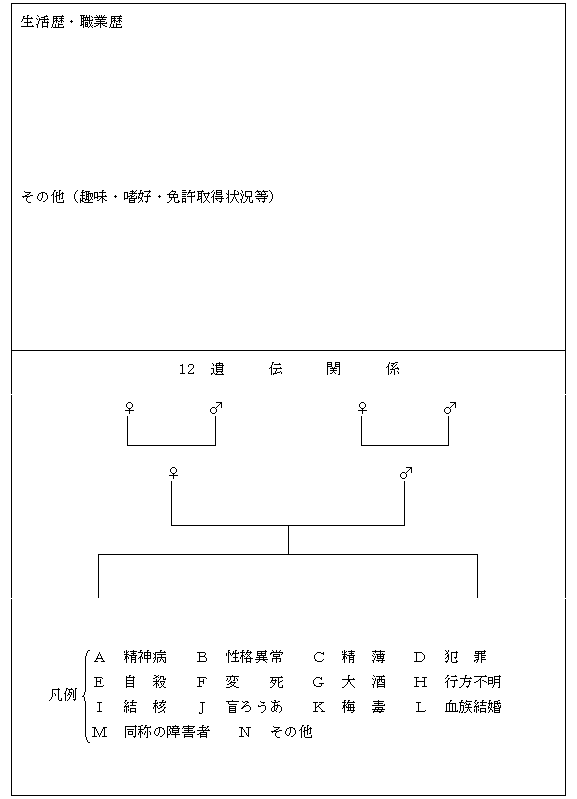
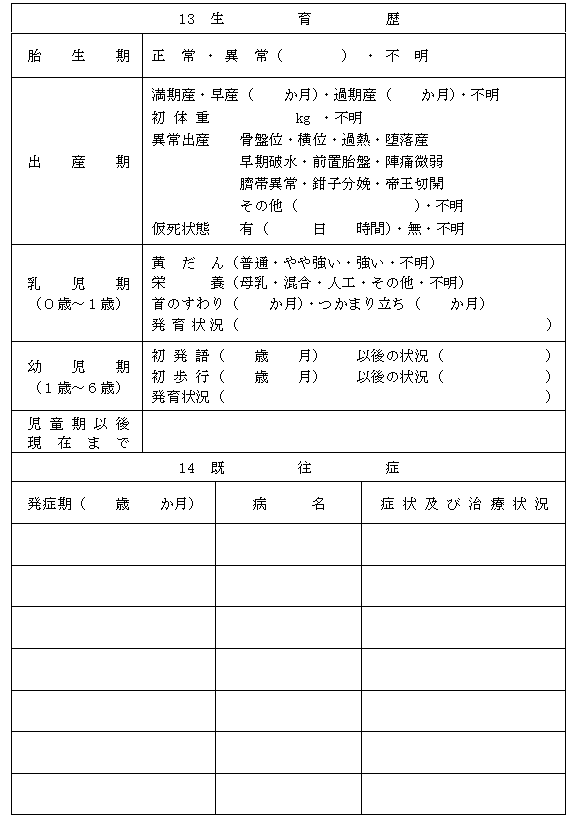
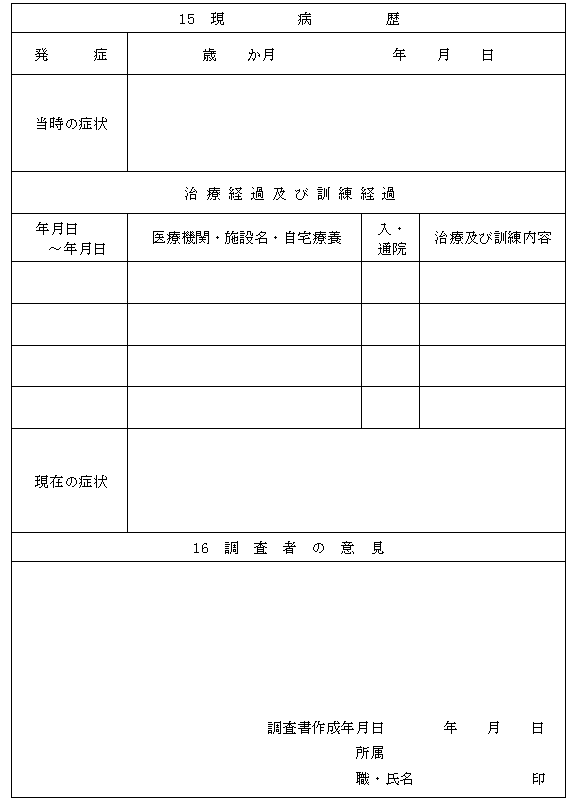 様式第27号
様式第27号
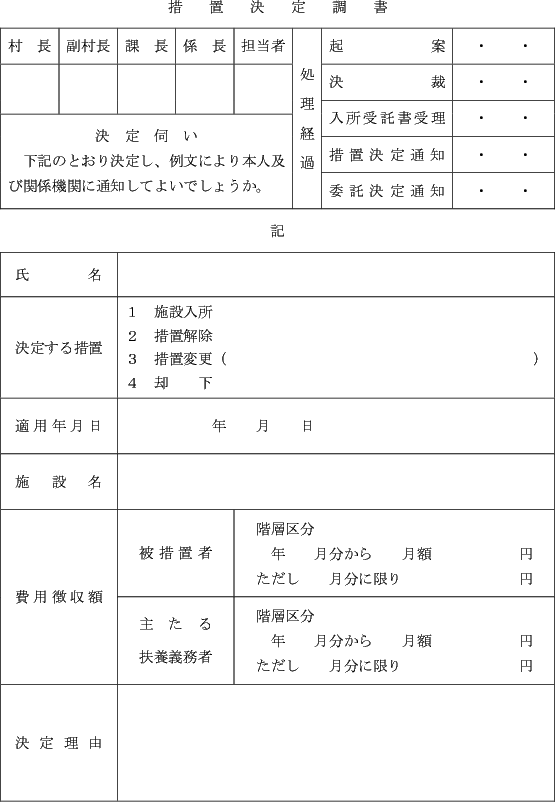 様式第28号
様式第28号
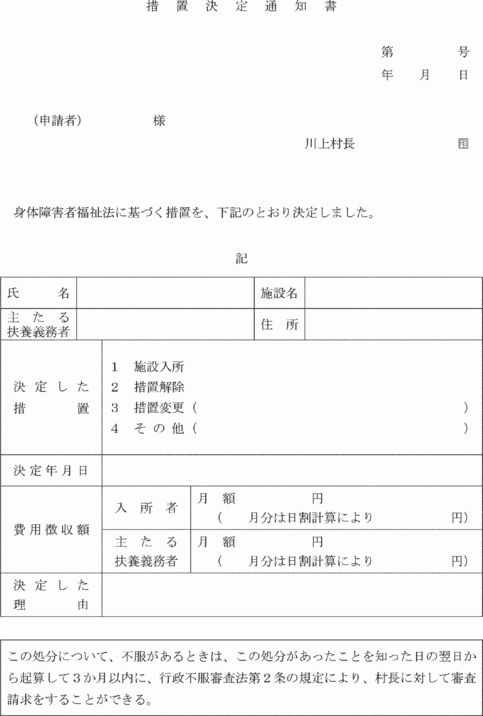 様式第29号
様式第29号
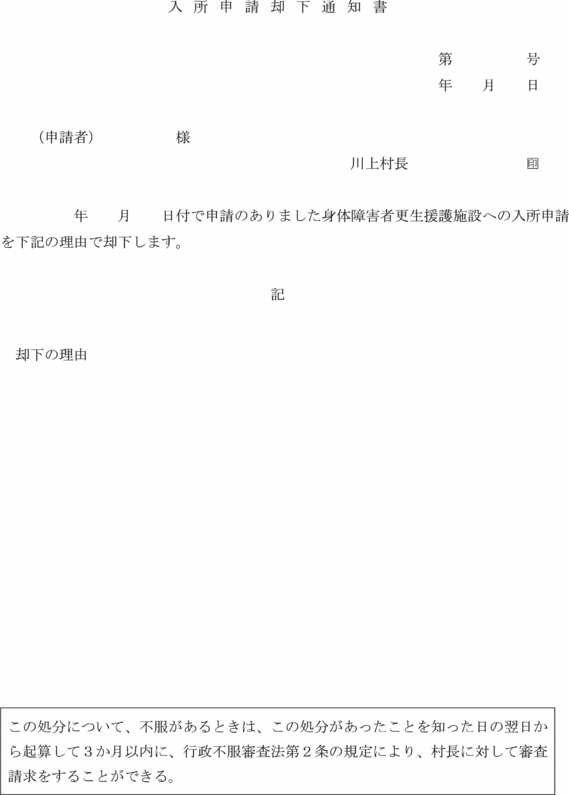 様式第30号
様式第30号
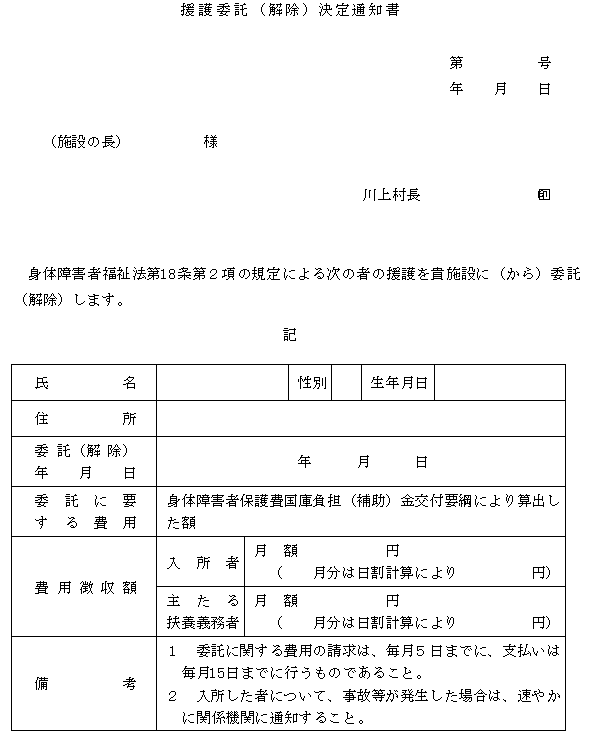 様式第31号
様式第31号
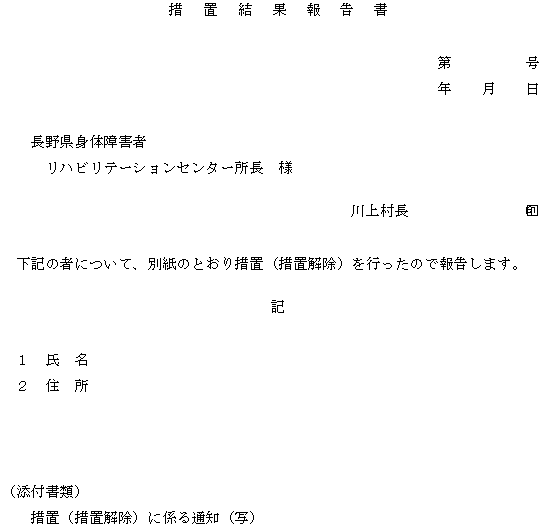 様式第32号
様式第32号
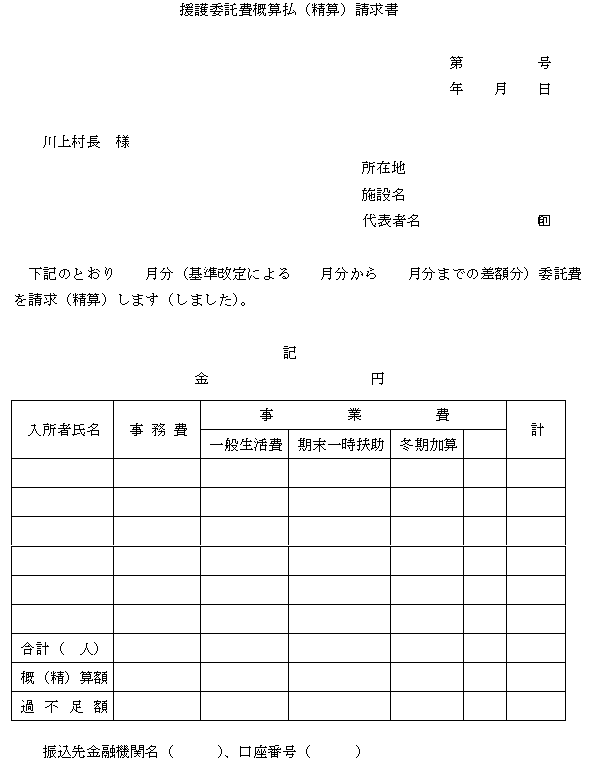 様式第33号
様式第33号
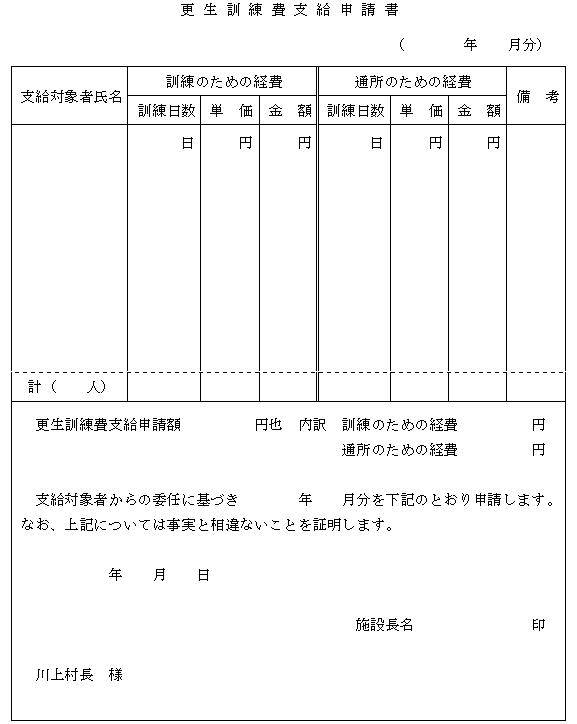 様式第34号
様式第34号
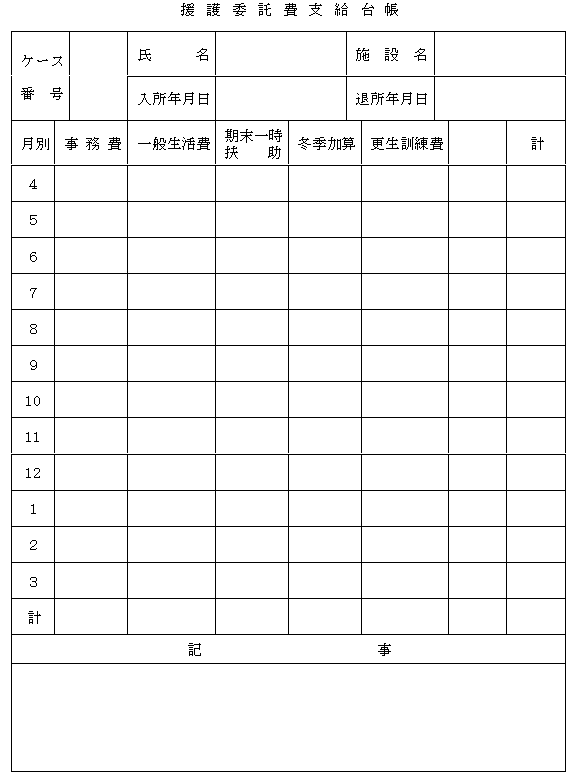 様式第35号
様式第35号
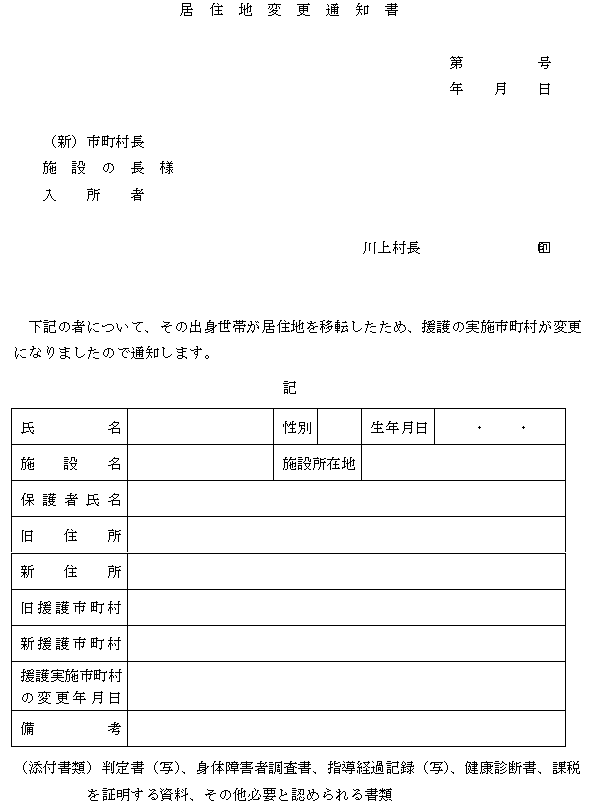 様式第36号
様式第36号
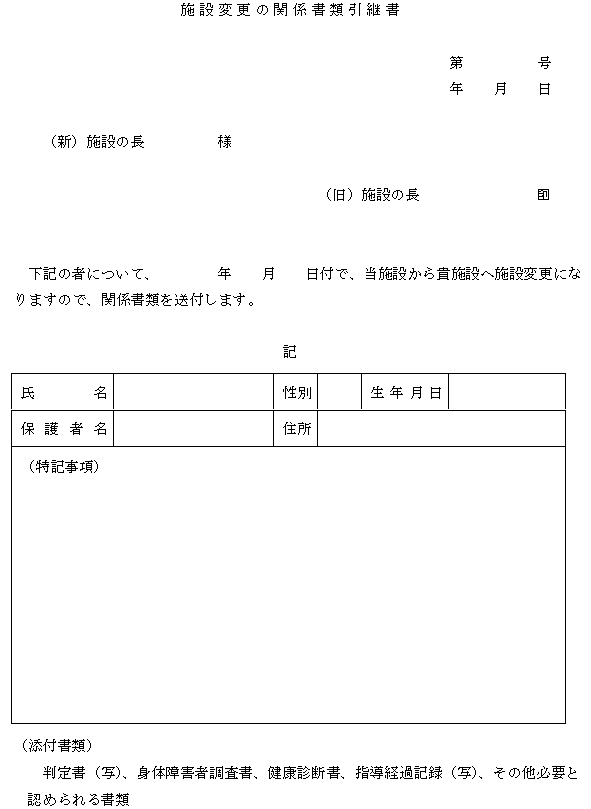 様式第37号
様式第37号
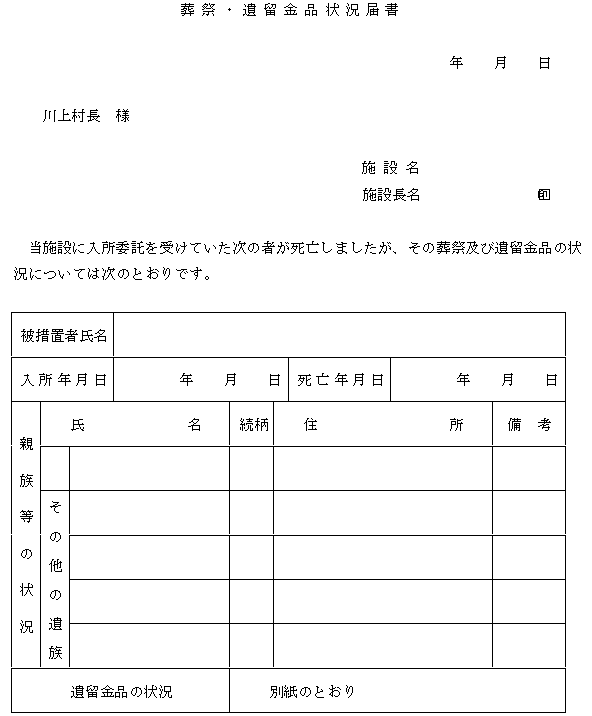
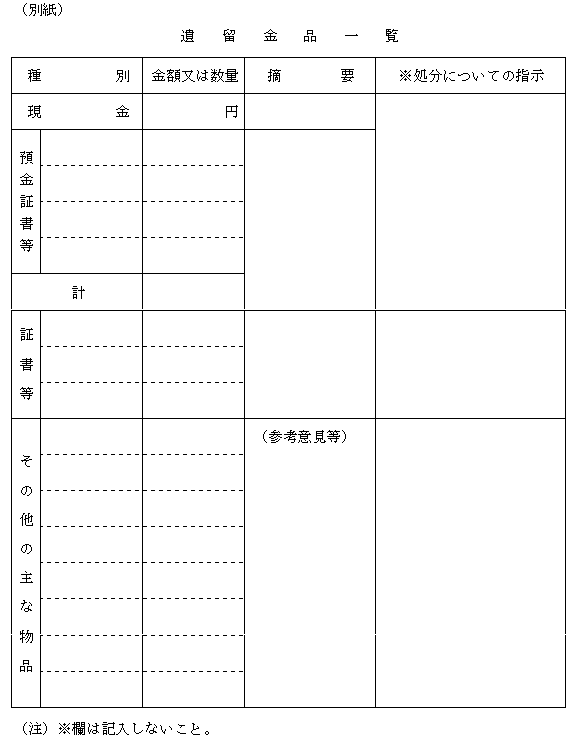 様式第38号
様式第38号
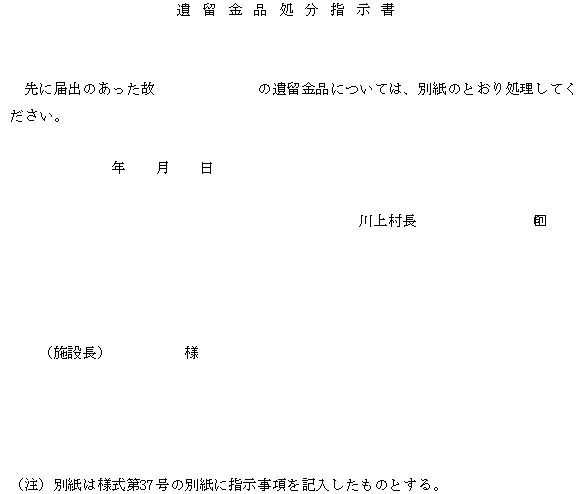 様式第39号
様式第39号
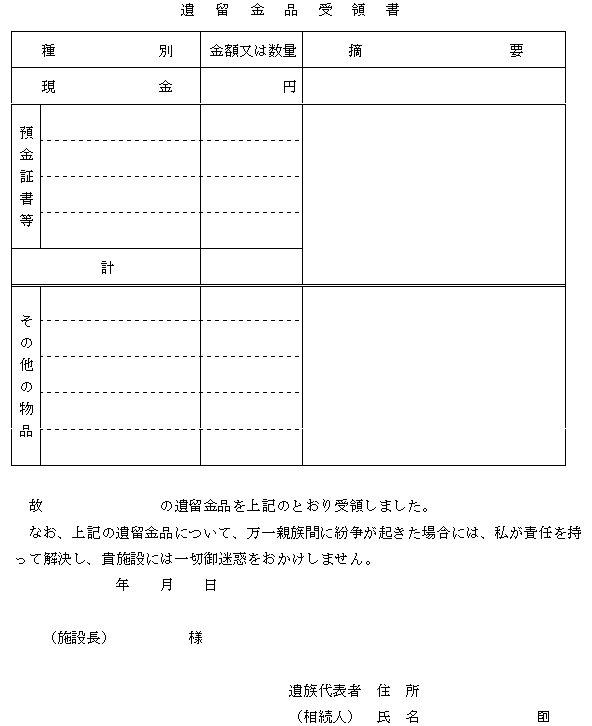 様式第40号
様式第40号
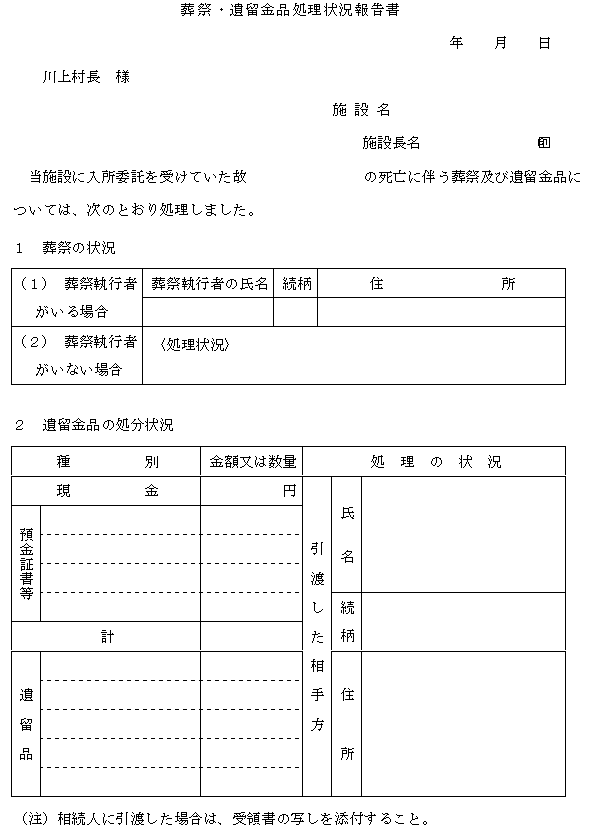 様式第41号
様式第41号
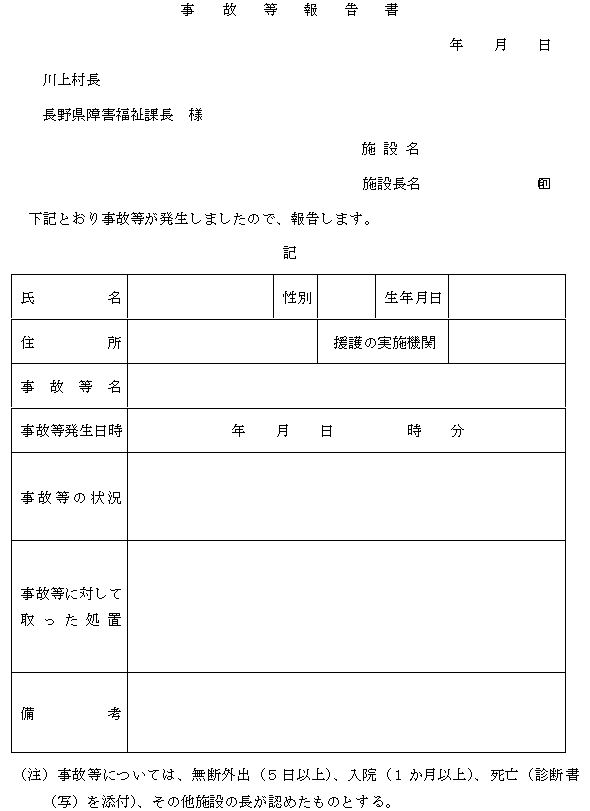 様式第42号
様式第42号
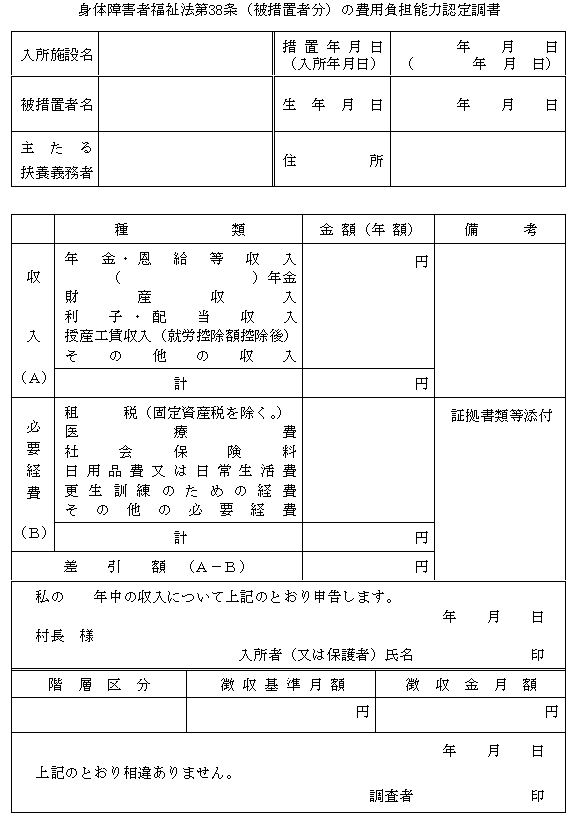 様式第43号
様式第43号
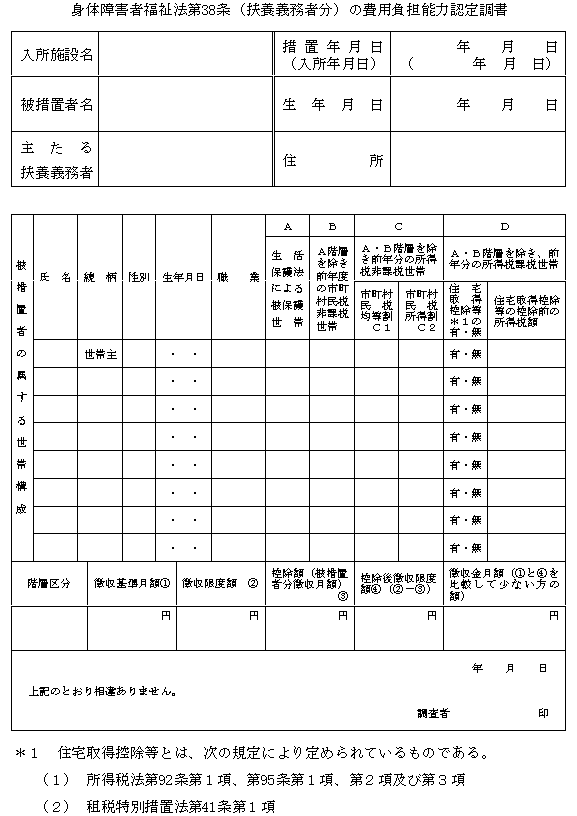 様式第44号
様式第44号
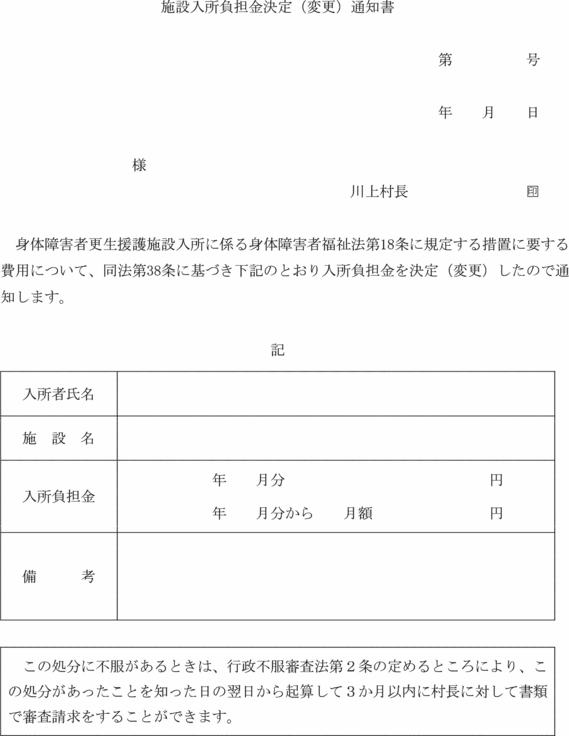
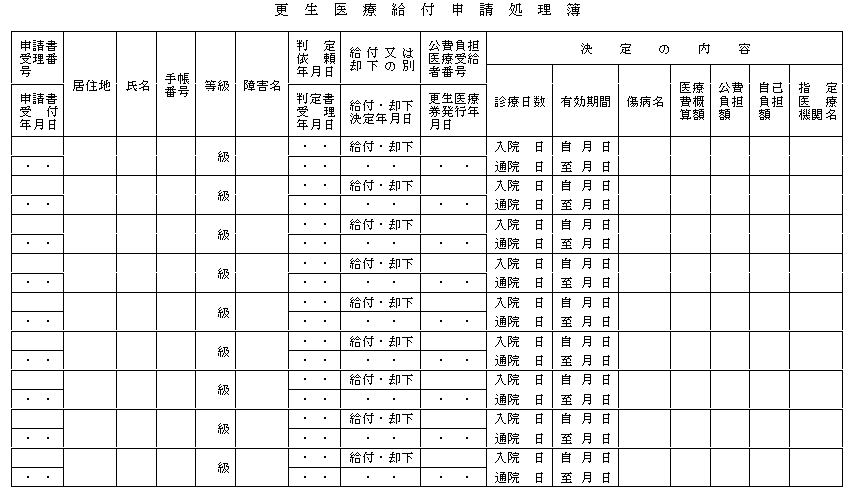 様式第2号
様式第2号
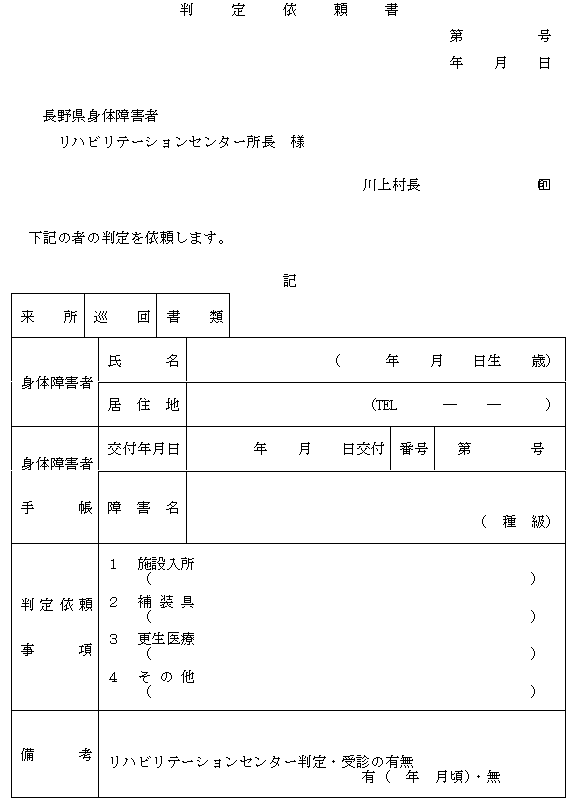 様式第3号
様式第3号
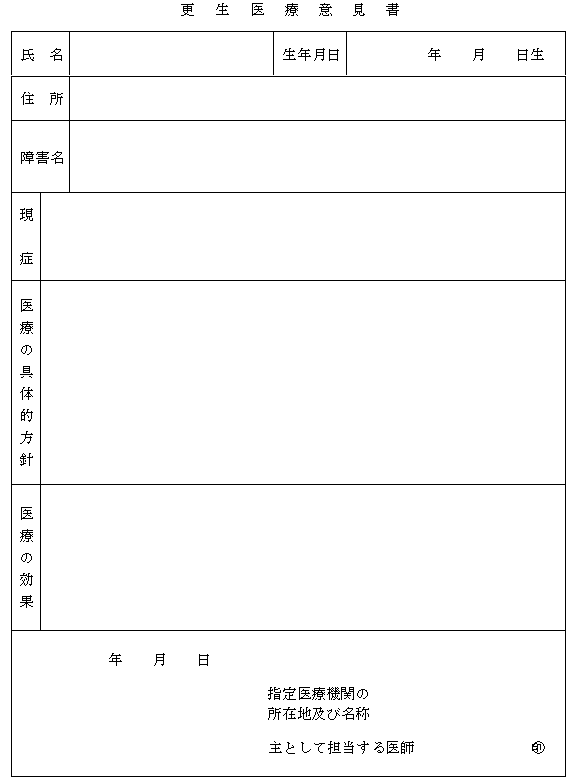 様式第4号
様式第4号
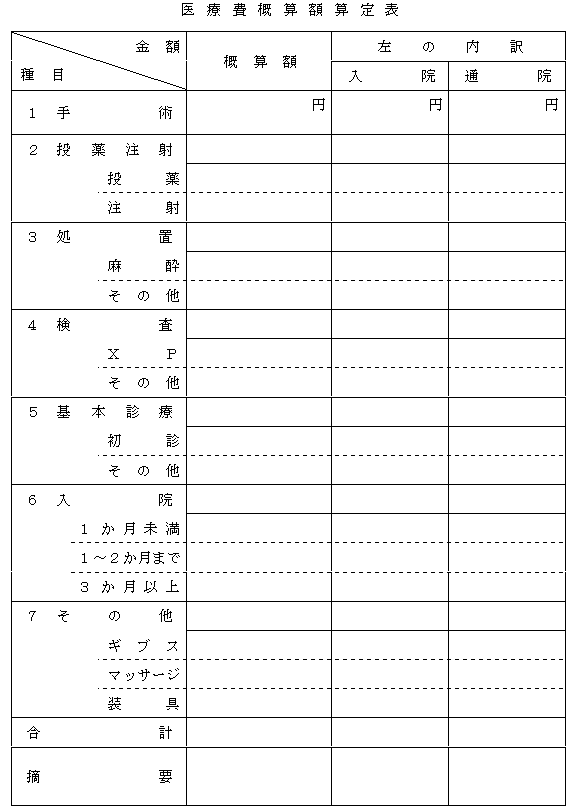 様式第5号
様式第5号
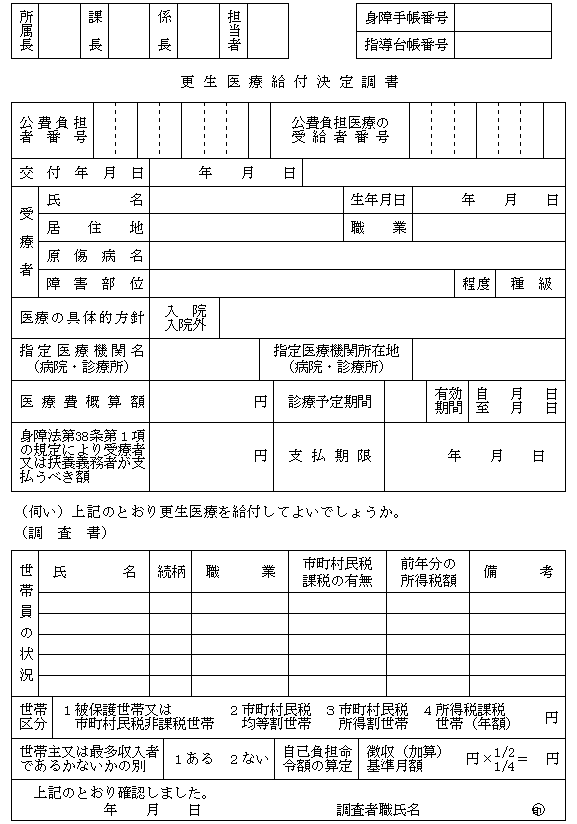 様式第6号
様式第6号
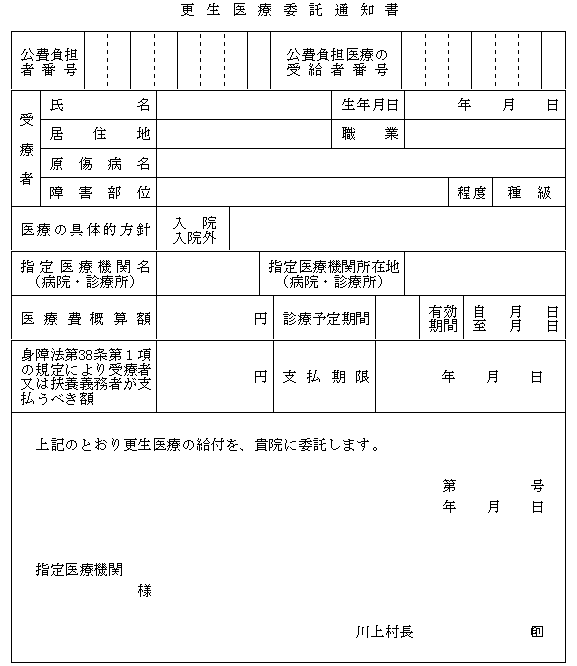 様式第7号
様式第7号
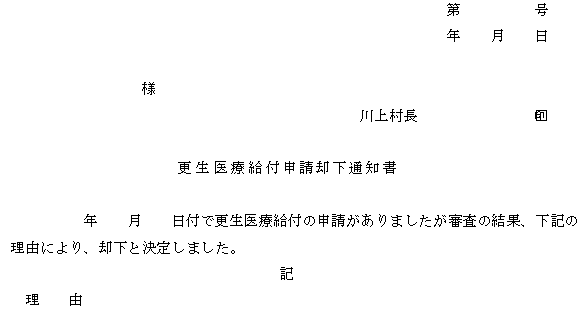 様式第8号
様式第8号
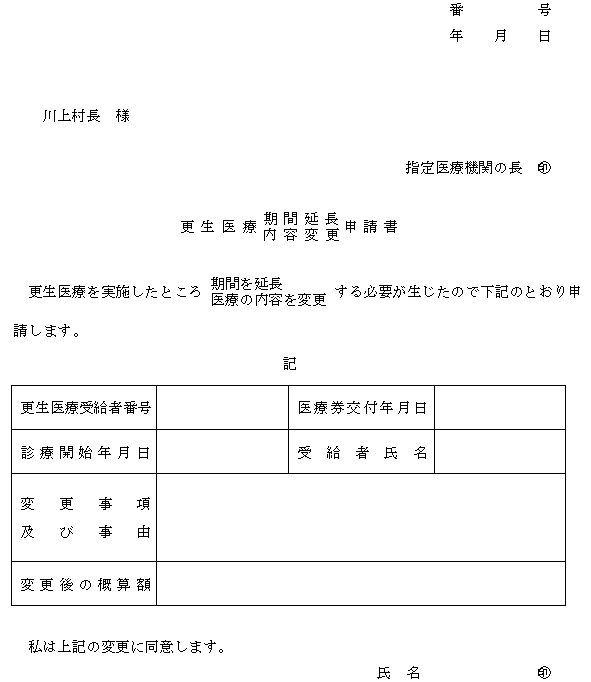 様式第9号
様式第9号
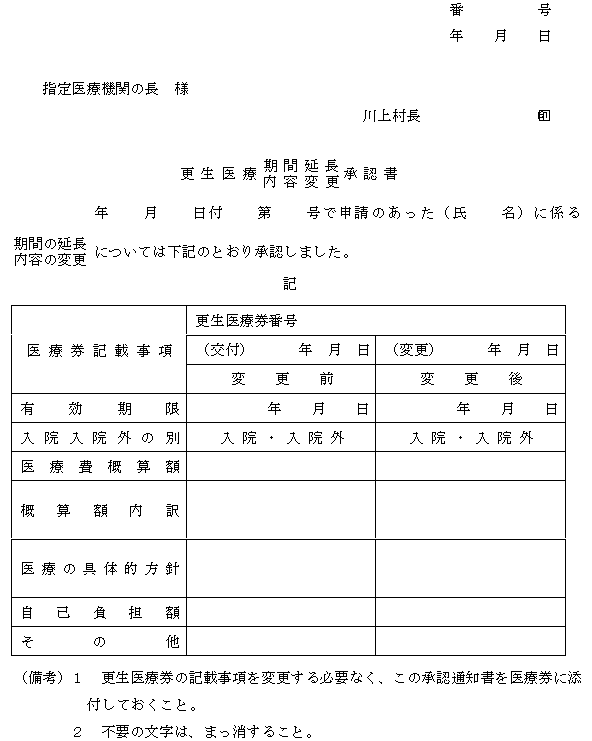 様式第10号
様式第10号
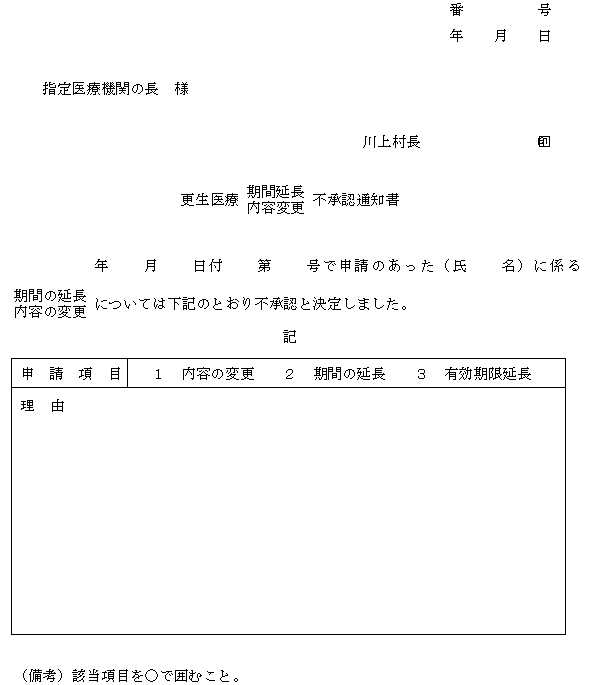 様式第11号
様式第11号
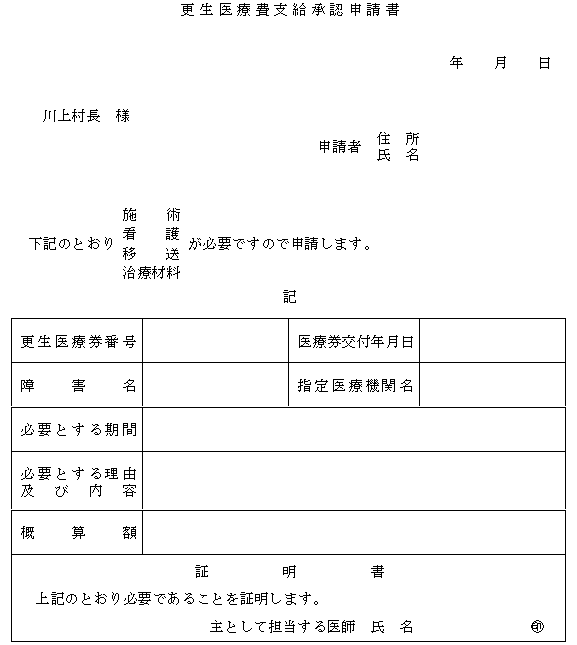 様式第12号
様式第12号
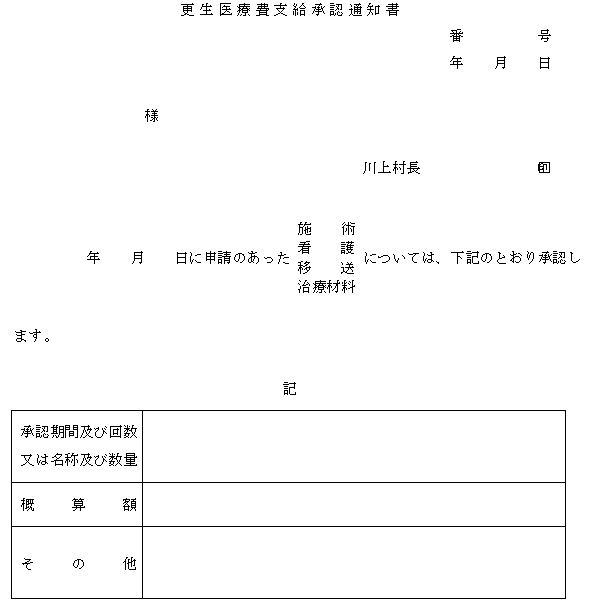 様式第13号
様式第13号
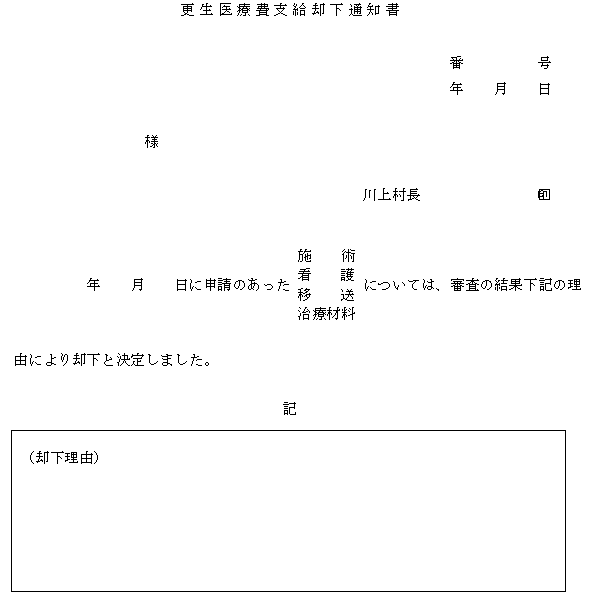 様式第14号
様式第14号
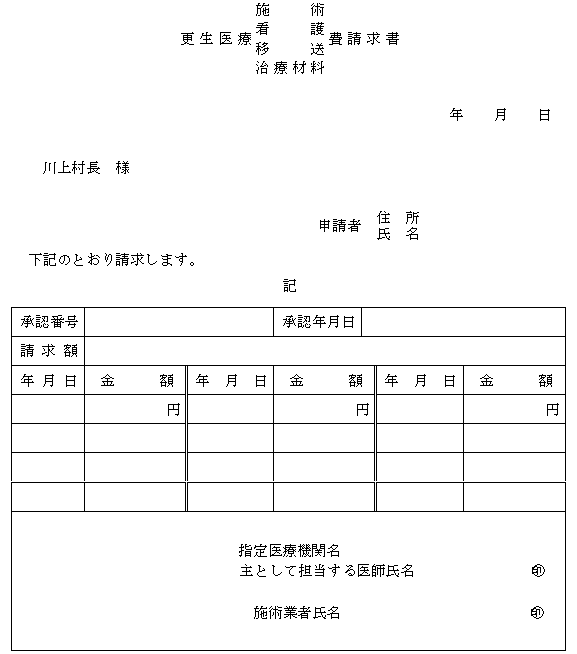 様式第15号
様式第15号
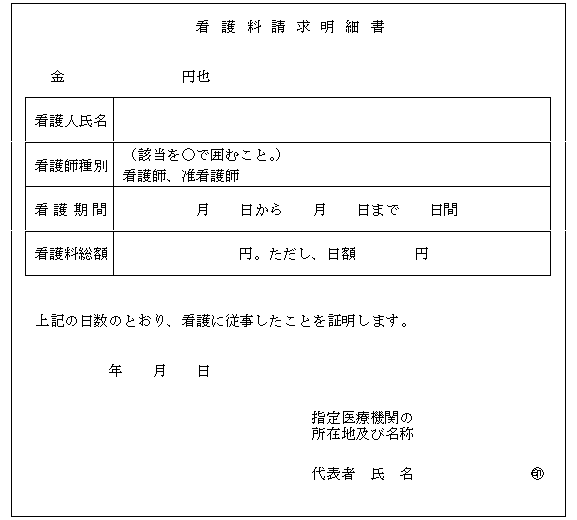 様式第16号
様式第16号
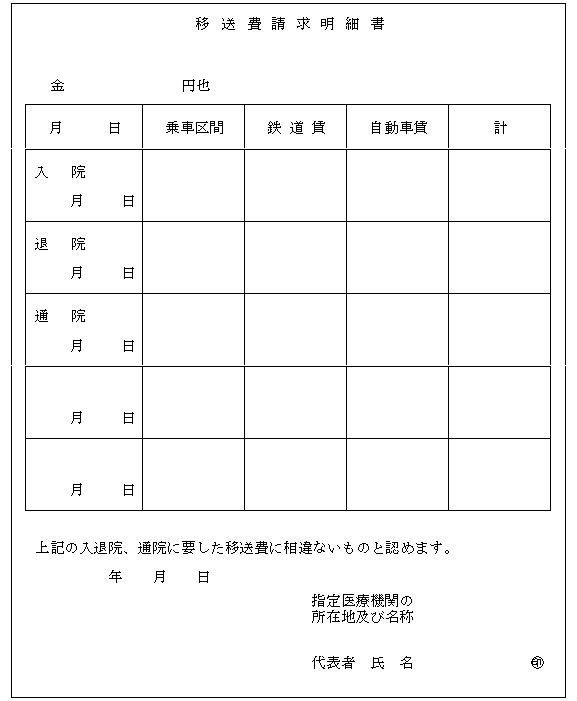 様式第17号
様式第17号
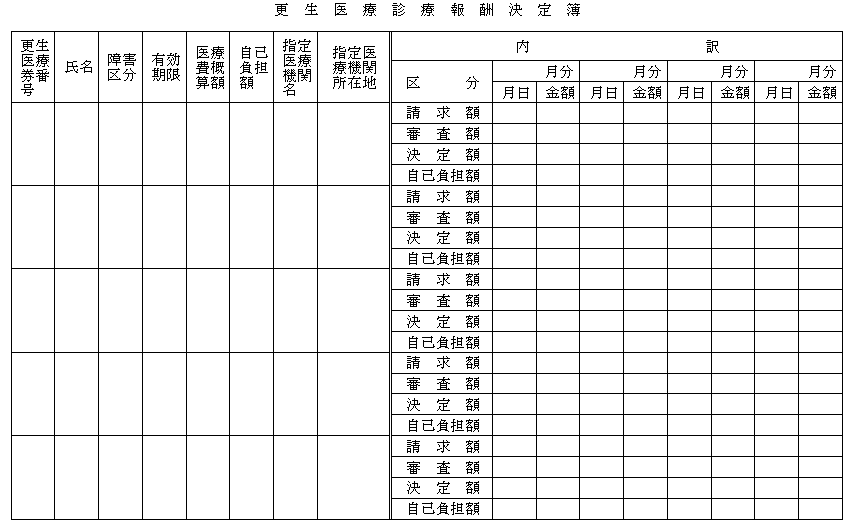 様式第18号から様式第23号まで 削除
様式第24号
様式第18号から様式第23号まで 削除
様式第24号
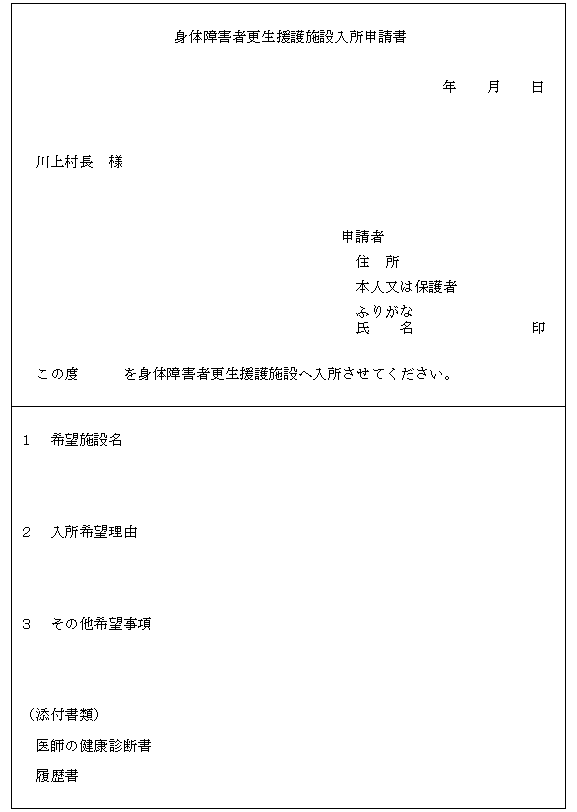 様式第25号
様式第25号
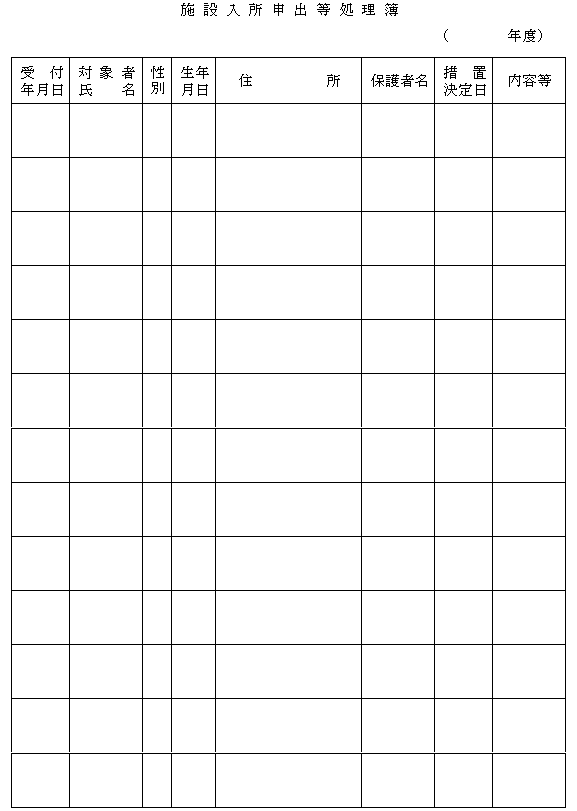 様式第26号
様式第26号
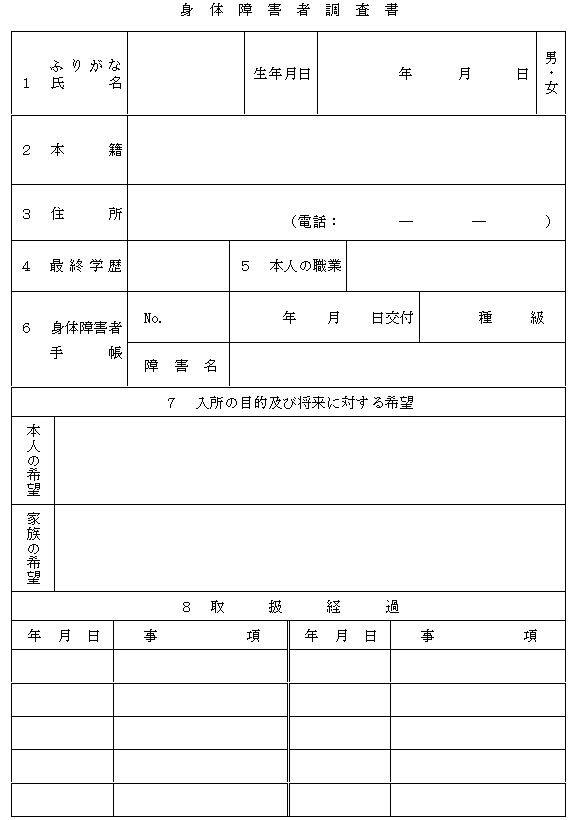
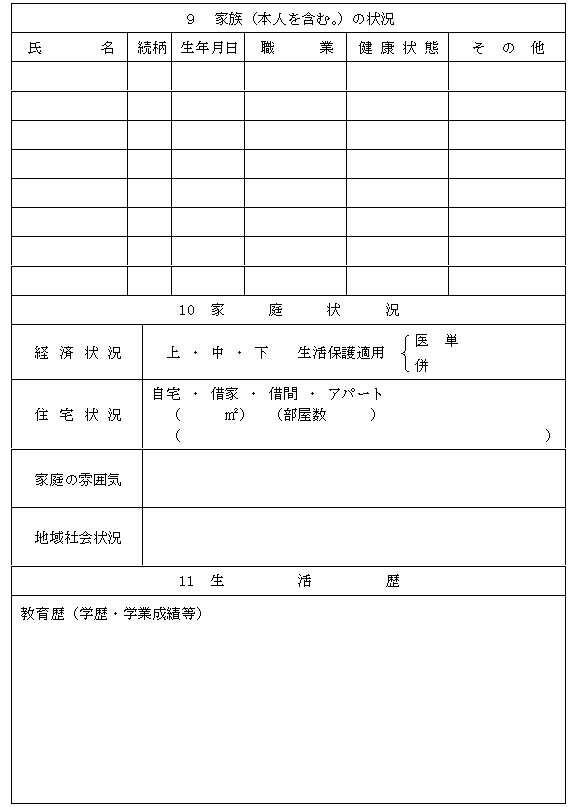
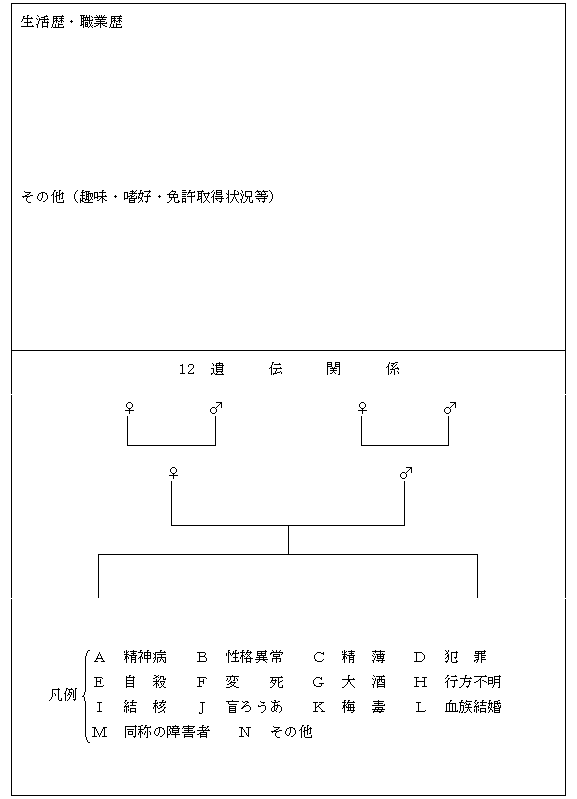
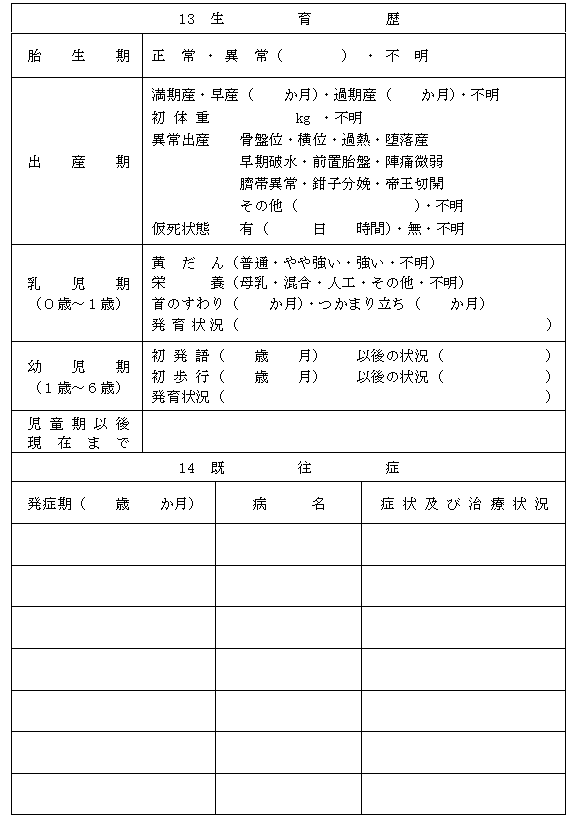
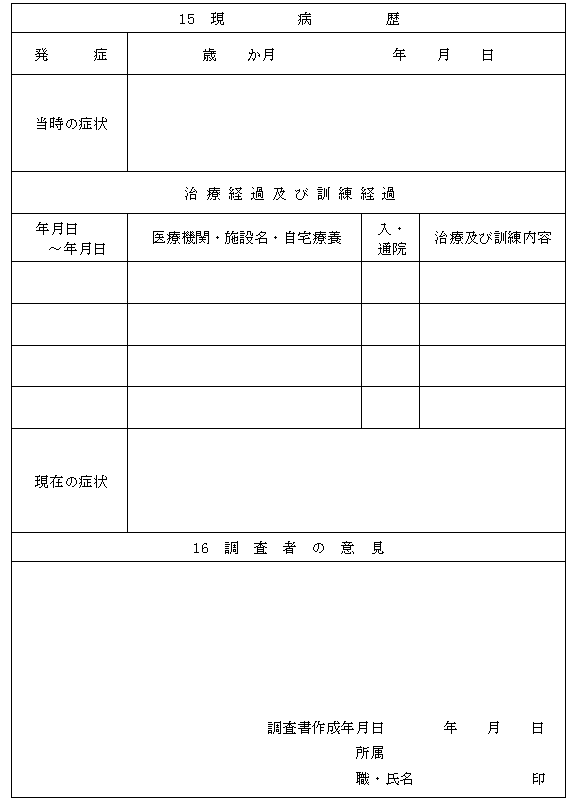 様式第27号
様式第27号
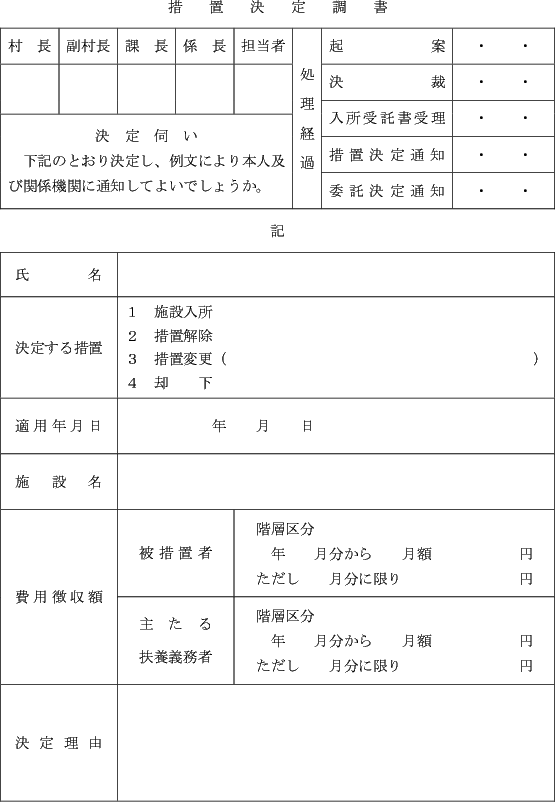 様式第28号
様式第28号
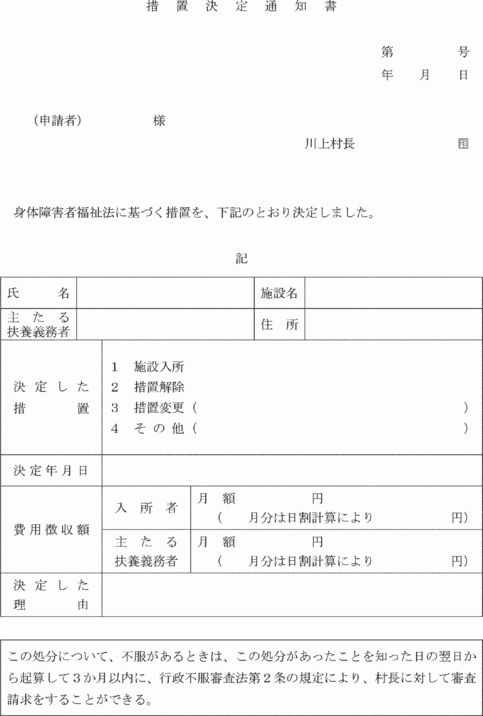 様式第29号
様式第29号
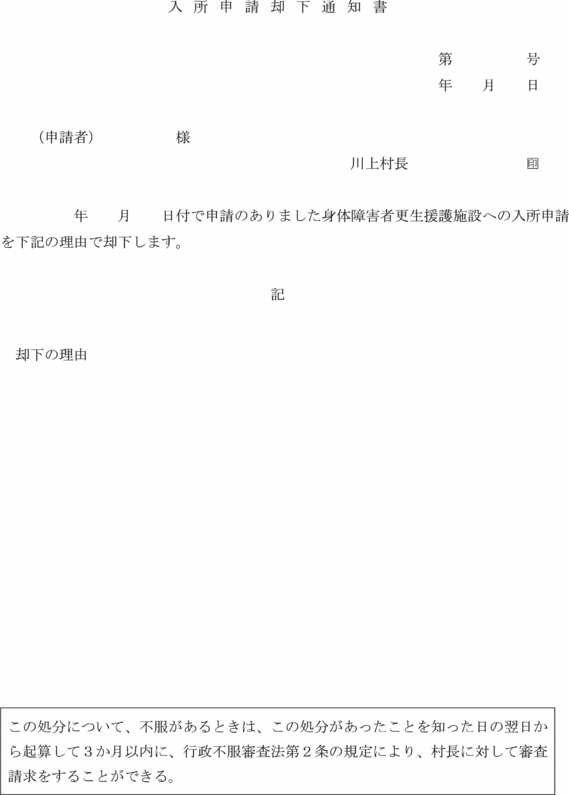 様式第30号
様式第30号
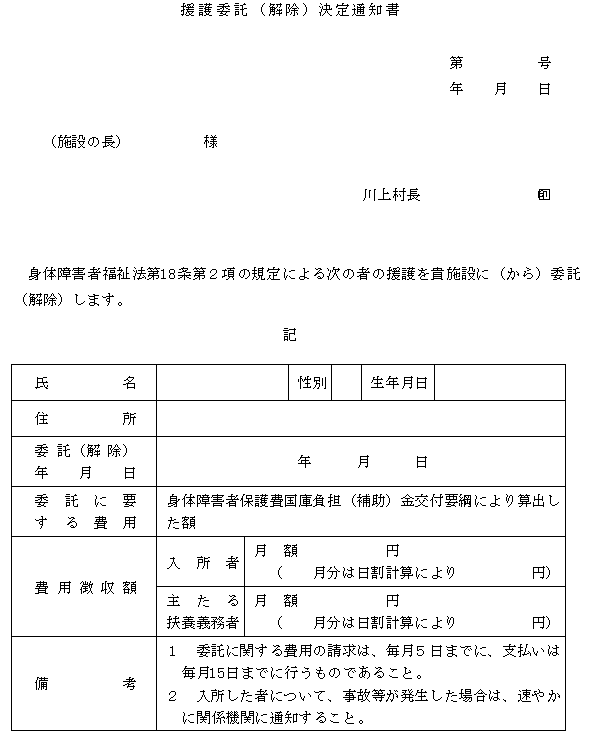 様式第31号
様式第31号
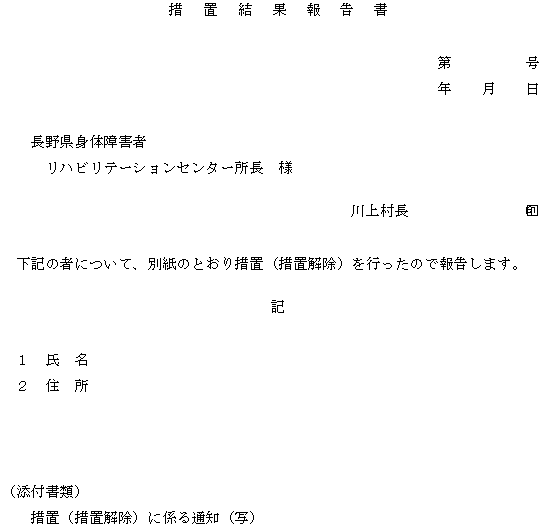 様式第32号
様式第32号
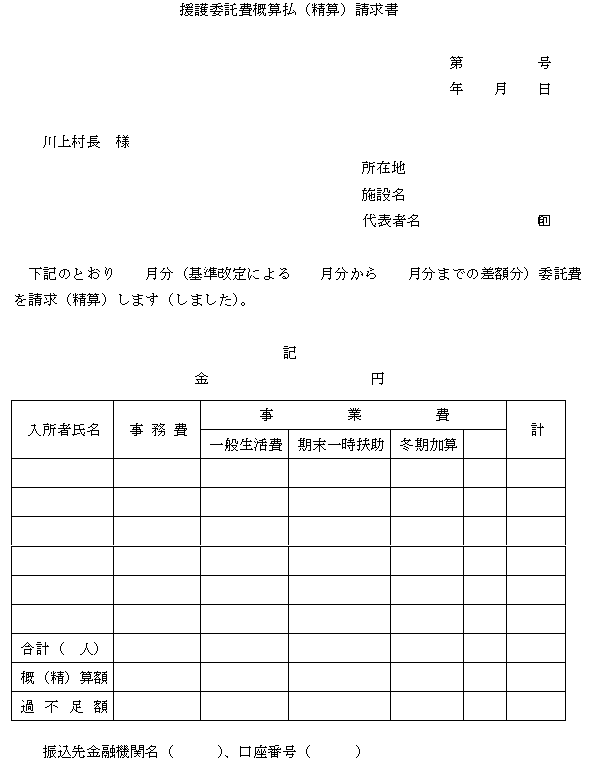 様式第33号
様式第33号
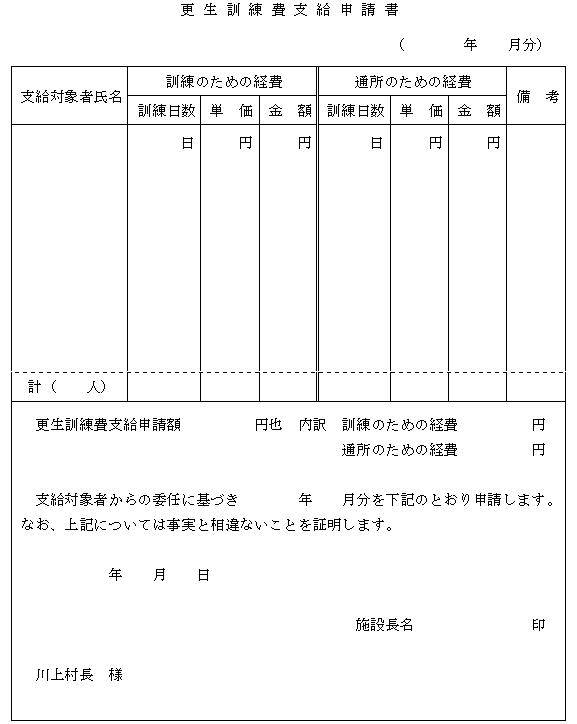 様式第34号
様式第34号
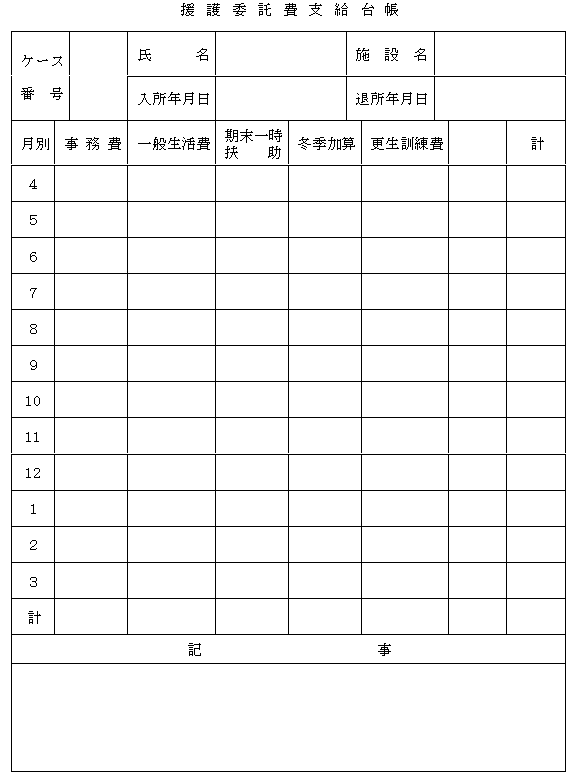 様式第35号
様式第35号
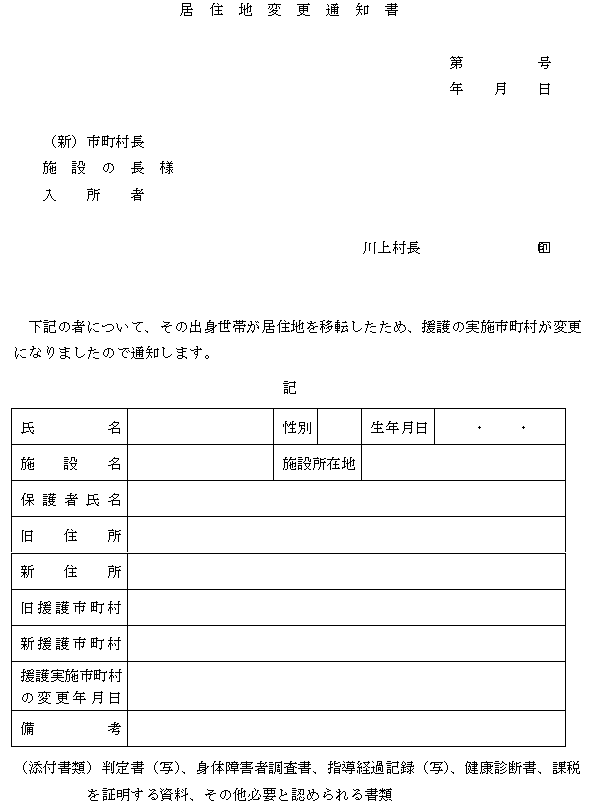 様式第36号
様式第36号
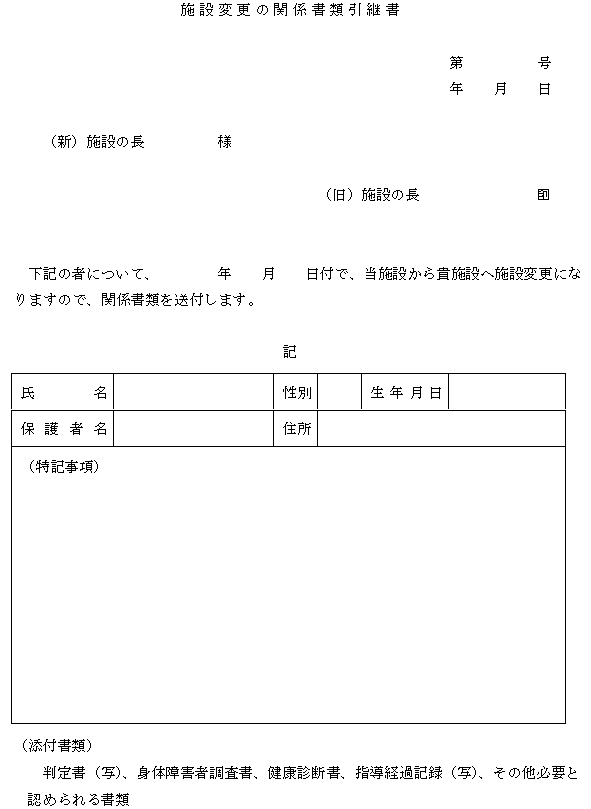 様式第37号
様式第37号
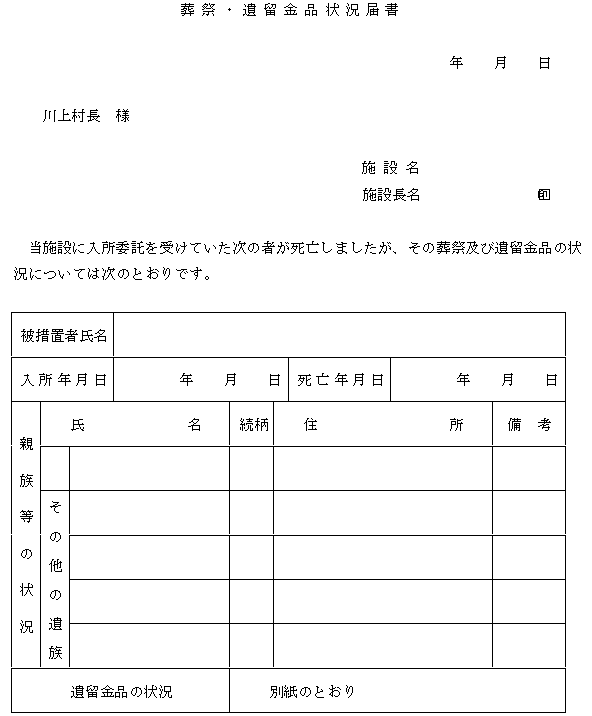
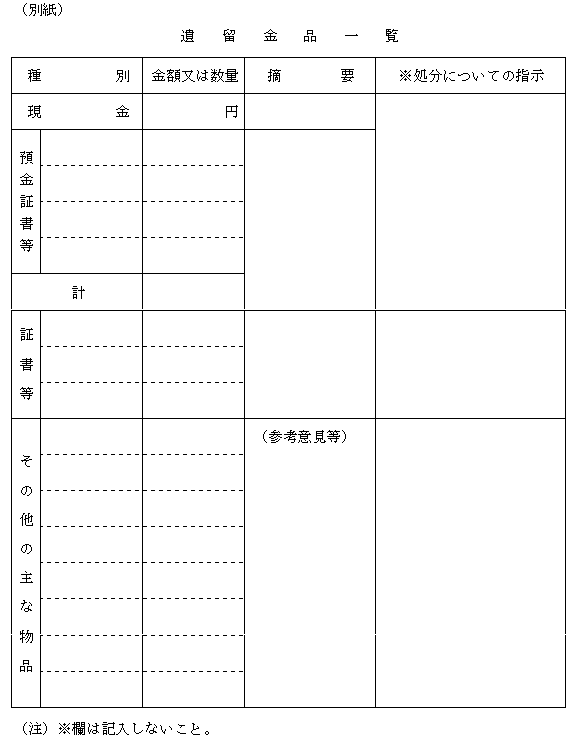 様式第38号
様式第38号
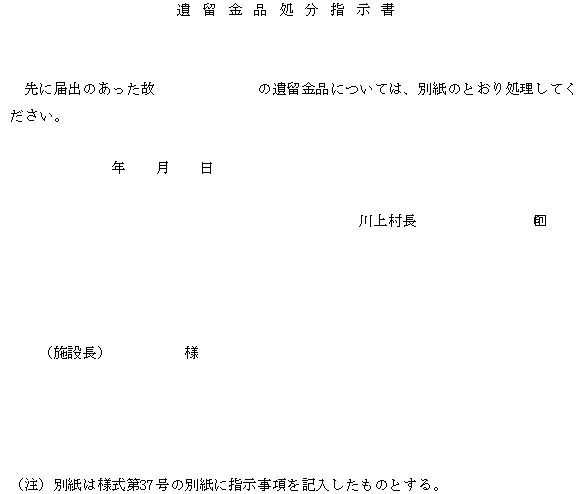 様式第39号
様式第39号
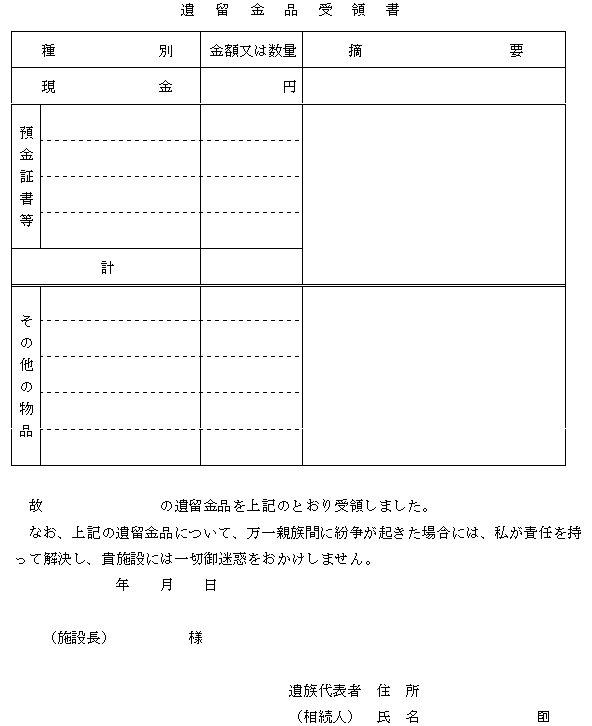 様式第40号
様式第40号
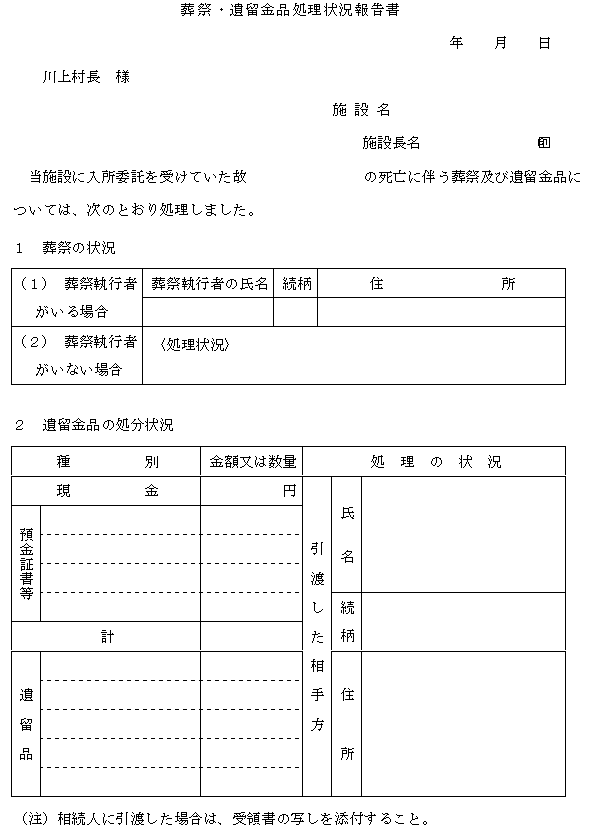 様式第41号
様式第41号
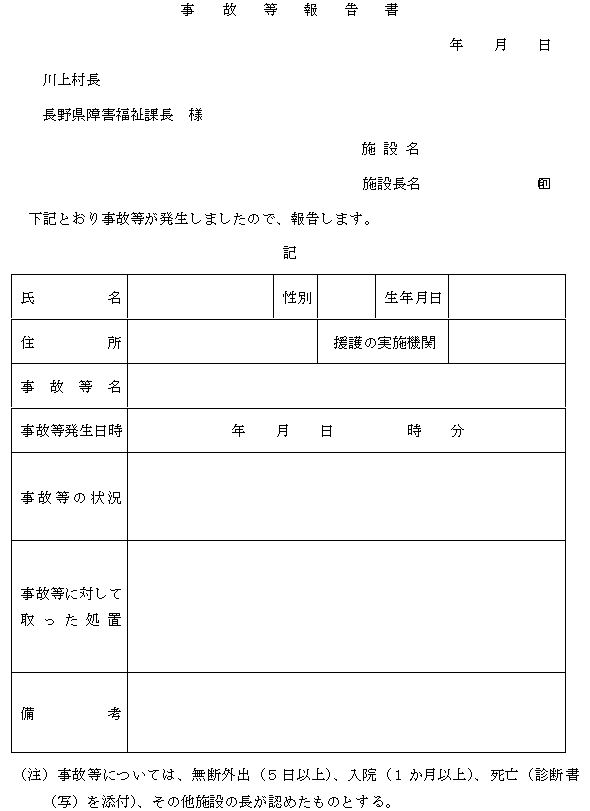 様式第42号
様式第42号
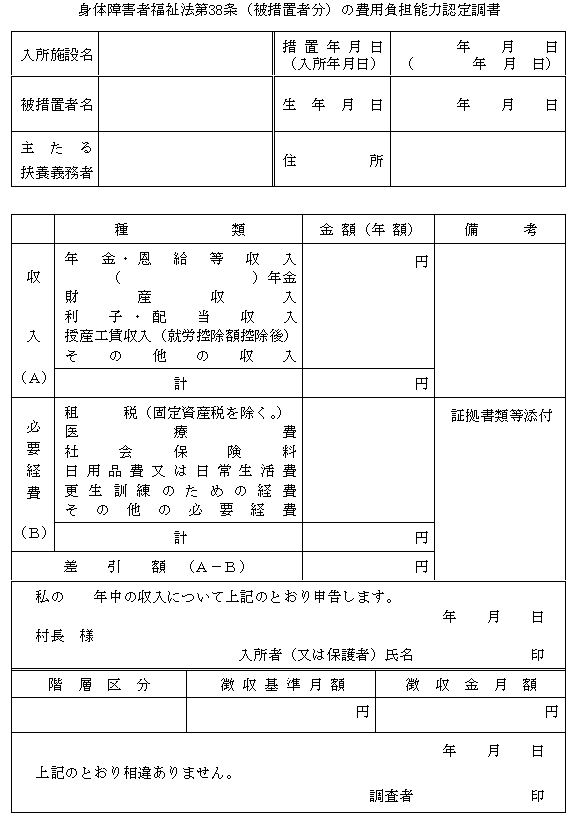 様式第43号
様式第43号
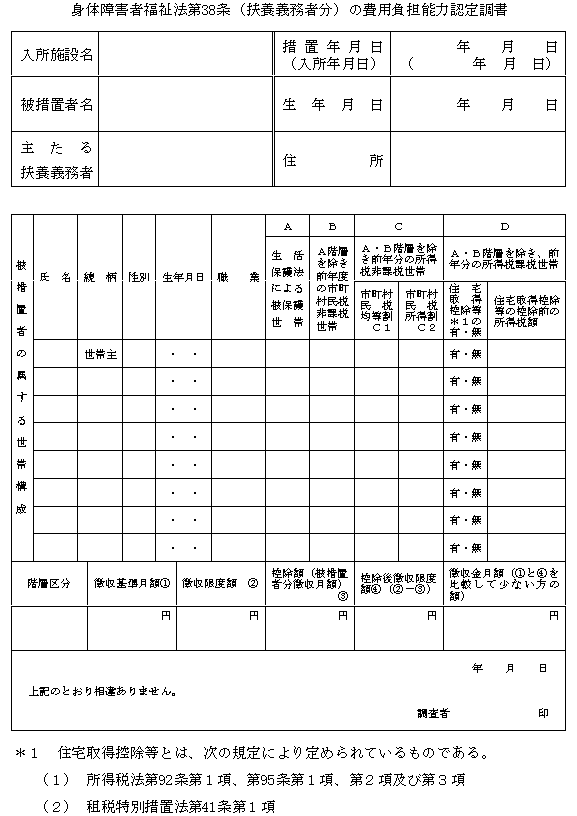 様式第44号
様式第44号